相続専門コラム
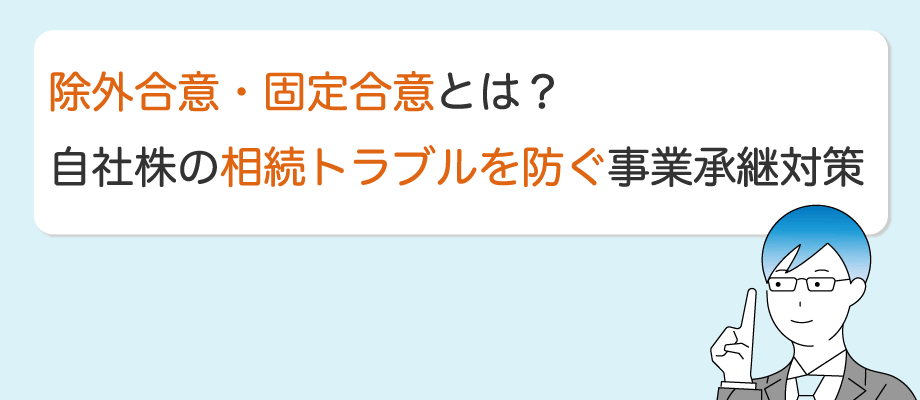
中小企業の事業承継で自社株を引き継ぐ際、遺留分を巡り思わぬトラブルが発生することがあります。
そこで経営承継円滑化法では「遺留分に関する民法の特例制度」を定め、自社株の除外合意や固定合意を可能にしています。これは遺留分の制約をあらかじめ取り除き、後継者に自社株を集中させる方法です。
今回の記事では、除外合意・固定合意の手続き方法とそれぞれのメリット・デメリットを解説します。「後継者に自社株をどう引き継げばいいのか、スムーズな事業承継の方法を探している」という方は、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

中小企業の事業承継では、後継者を1人に定め、生前贈与や相続(遺贈)によって自社株を引き継がせるケースが少なくありません。
しかし、この自社株承継は相続時に思わぬ金銭トラブルを引き起こします。具体的には、他の相続人から後継者に対して「自分たちの取り分が少なすぎる」と主張され、金銭を要求される可能性があります。

金銭を要求されたとき、後継者に目立った財産がなければ自社株で補てんするしかありません。結果として、せっかく承継した事業経営の不安定化につながってしまいます。こうした金銭トラブルと経営リスクに対応するための対策が「遺留分に関する民法の特例」における除外合意と固定合意です。
| 除外合意 | 固定合意 | |
|---|---|---|
| どんな事業承継に有効か | 経営者、後継者ともに資産の大半が自社株(相続人に渡せる財産が他にない) | 業績が好調で将来的に株価が上がる見込みがある |
| 合意内容 | 遺留分の計算に自社株を入れないようにする | 自社株の相続税評価額を事前に決めた価格に固定しておく |
| 対応できるリスク | 遺留分侵害で他の相続人から金銭を要求されるリスク | 遺留分侵害で他の相続人から金銭を要求されるリスク |
そもそも遺留分とは何か、遺留分がなぜ金銭トラブルと経営リスクに発展するのか、詳細は下記で解説しましょう。

被相続人が特定の相続人に全財産を遺贈してしまうと、残された配偶者や子どもの生活が立ちゆかなくなる可能性があります。そこで民法では、兄弟姉妹以外の相続人に対して「最低減の相続割合=遺留分」を受け取る権利を保障しています。

【遺留分の割合】

| 相続人のパターン | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ または 子ども1人のみ | 全額 | 2分の1 |
| 配偶者と子ども | ・配偶者 2分の1 ・子ども 2分の1 | ・配偶者 4分の1 ・子ども 4分の1 |
| 配偶者と子ども2人 | ・配偶者 2分の1 ・子どもA 4分の1 ・子どもB 4分の1 | ・配偶者 4分の1 ・子どもA 8分の1 ・子どもB 8分の1 |
| 子ども2人のみ | ・子どもA 2分の1 ・子どもB 2分の1 | ・子どもA 4分の1 ・子どもB 4分の1 |
| 子ども3人のみ | ・子どもA 3分の1 ・子どもB 3分の1 ・子どもC 3分の1 | ・子どもA 6分の1 ・子どもB 6分の1 ・子どもC 6分の1 |
先代経営者の相続人が後継者1人だけであれば、自社株を集中させても遺留分が問題になることはありません。しかし、先代経営者に複数の相続人がいて、さらに自社株以外に目立った財産が無い場合は、遺留分侵害になることがあります。
例として遺産総額が6,000万円あると仮定し、遺留分侵害になるケースを解説します。ここでの先代経営者は父親、後継者は長男で、他に2人の相続人(次男・長女)がいるとします。この場合、相続発生時のそれぞれの遺留分は下記表のとおりです。
| 相続人のパターン | 遺産6,000万円の遺留分 |
|---|---|
| 子ども3人 | ・長男(後継者):1,000万円(6分の1) ・次男:1,000万円(6分の1) ・長女:1,000万円(6分の1) |
つまり、子どもたちはそれぞれ最低でも1,000万円の遺産を受け取る権利を有しています。
ところが、実際に相続が発生した際、遺産6,000万円のうち5,000万円は自社株でした。事業を引き継ぐ長男が自社株をすべて受け取ると、次男と長女がそれぞれ受け取れる遺産は1,000万円もありません。
【遺産6,000万円の相続割合】

次男・長女が残りすべての遺産(預貯金)を受け取ったとしても、それぞれの遺留分1,000万円を下回ります。これが遺留分侵害です。先代経営者(被相続人)の遺産の大半が自社株で、かつ自社株の時価評価額がそれなりに高いと、このように後継者が他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
2019年7月1日に施行された改正民法により、遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対して侵害額に相当する金銭を請求できるようになりました。
先ほどのケースで言えば、長男に遺留分を侵害された他の相続人2人(次男・長女)は、自分たちの取り分1,000万円を長男に請求する権利があります。実際の請求を「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分を請求されたとき、後継者に目立った財産がない場合は自社株を渡す方法しかありません。しかし、関係のない親族に株式を持たせることは、経営権の不安定化につながる恐れがあります。
このようなリスクを回避して自社株を後継者に集中させる方法が「除外合意」「固定合意」です。

遺留分に関する民法の特例とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)で定められた支援措置です。
遺留分トラブルを防いで自社株を後継者に集中させる方法に「除外合意」「固定合意」があり、任意で「付随合意」も選択できます。
除外合意とは、後継者と推定相続人(先代経営者の死亡時に相続人になる人)の全員が、「自社株を遺留分の算定対象から外す」合意をすることです。相続発生前に除外合意をしておけば、自社株は遺留分の対象財産から除外できます。

よって、相続発生後、推定相続人から「やっぱり気が変わったから遺留分の遺産を渡して」と主張されるリスクに対処できます。自社株以外に目立った財産がなく、遺留分侵害の可能性が高いときに有効な方法です。
固定合意とは、「遺留分を計算する際の自社株の価額を、後継者と推定相続人全員が合意した時点の評価額に固定する」という合意です。除外合意と異なり、自社株は遺留分の対象財産に含めます。ただし、今後急激に自社株の評価が上昇したとしても、その上昇分は遺留分の対象から除外されます。

よって、株式の思わぬ上昇による遺留分侵害リスクに対処可能です。業績が好調で、将来的に企業成長による株価上昇が期待できるときに有効な方法です。
付随合意とは、除外合意または固定合意とあわせて、次の内容に合意するものです。
1と3は、自社株だけではなく他の財産も遺留分から除外する取り決めで、合意の対象にできる財産の種類や額には制限がありません。2の措置とは、当事者間の衡平を図るために行うものです。たとえば、「後継者から後継者以外の推定相続人に対して一定の金銭を支払う」ことなどを定め、除外合意などを行うことで推定相続人だけが不利益を被る状態になることを避けるようにします。
付随合意は単独で行うものではなく、あくまで除外合意または固定合意に任意で付随できるものです。
遺留分侵害による相続トラブルを防ぐ方法には、「遺留分事前放棄制度」もあります。
ただし、この事前放棄制度は除外合意・固定合意と異なり、後継者以外の推定相続人が自ら家庭裁判所に申し立てなければなりません。遺留分を放棄することに何のメリットもない推定相続人が自ら面倒な手続きをする必要があり、明らかに使い勝手が悪い制度と言えます。
その点、除外合意や固定合意は、遺留分の制限によってメリットを受ける後継者主導で手続き可能です。

遺留分に関する民法の特例に基づき除外合意や固定合意を行う際の流れは下記のとおりです。

ここでは、それぞれのステップを解説しましょう。
除外合意・固定合意を受けるには、会社・先代経営者・後継者それぞれが下記の要件を満たす必要があります。
【民法特例の適用要件(会社の経営承継の場合)】
なお、「後継者」は先代経営者の相続人である必要はありません。そのため、親族以外が後継者となり自社株を取得する際も、要件さえ満たせば本特例を受けることが可能です。
これらの適用要件を満たしたうえで、先代経営者の推定相続人全員の合意を得ることができれば、手続きを進められます。なお、ここでの「推定相続人全員」に兄弟姉妹は含まれません。推定相続人になる可能性があるのは、遺留分の権利がある配偶者や子ども(およびその代襲相続人)、または直系尊属(祖父母)です。
適用要件を確認して合意を取り付けたら、合意から1か月以内に経済産業大臣に確認申請を行います。この申請は後継者単独で手続き可能です。
すべての書類を揃えたうえで、経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課まで提出してください。
| 主な作成書類 | ・確認申請書 ・確認証明申請書 ・合意書 |
主な添付書類 | ・定款の写し ・株主名簿の写し ・登記事項証明書(申請日前3か月以内) ・従業員数証明書 ・貸借対照表など前3事業年度の計算書類 ・上場会社等でない旨の誓約書 ・印鑑証明書(申請日前3か月以内) ・先代(現在の)経営者、推定相続人全員および後継者の戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可) ・先代(現在の)経営者の住民票の写し(申請日前3か月以内) ・(固定合意の場合のみ)税理士等の固定価額の証明書 |
なお、確認申請書、確認証明申請書以外の書類については、申請者の希望により原本の還付を受けることが可能です。還付を希望する際は、原本とあわせてその写しを添付してください。特に戸籍謄本は、この後の家庭裁判所への申し立て手続きで必要になるため、原本の還付を受けておくことをおすすめします。
また、先代経営者については、原則として「出生日から合意日までの連続した戸籍謄本」が必要です。すべての戸籍の取得が難しい場合、法定相続情報一覧図で代替することも可能です。
作成書類(確認申請書、確認証明申請書、合意書)の様式はこちらのページからダウンロードできます。リンク先の「3.遺留分に関する民法の特例」の「手続きについて」の申請様式をご覧ください。ここでは、合意書の一例を紹介します。
合意書は、下記の内容を含めて作成します。
【後継者が推定相続人である場合】
合意書のひな形は下記のページからダウンロードできます。
「3.遺留分に関する民法の特例」>「手続きについて」の申請様式をご覧ください。
確認申請後、経済産業大臣から「確認書」の交付を受けます。後継者は確認を受けた日から1か月以内に「先代経営者の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立てを行います。
申し立ての際に必要な書類は下記のとおりです。
| 申し立てに必要な書類 | 主な添付書類 |
|---|---|
| 申立書 | ・経済産業大臣の作成に係る確認証明書 ・推定相続人の人数分の合意書の写し ・推定相続人全員の戸籍謄本 ・先代(現在の)経営者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
参考:裁判所「遺留分の算定に係る合意の許可」
なお、申し立ての際は「収入印紙800円分」と「連絡用の郵便切手」が必要です。郵便切手は申し立てを行う家庭裁判所にて確認してください。管轄の裁判所はこちらのページで確認可能です。
申立書の様式はこちらでダウンロード可能です。
家庭裁判所は、合意が当事者全員の真意により行われていることを確認したうえで許可の審判を確定します。許可の審判が確定した時点で合意の効力が発生します。

除外合意等のメリット・デメリットを解説します。
メリットは自社株の分散リスクを抑えて経営の不安定化を防ぐ点にあります。
株主が複数に分散すれば、意思決定に遅れが生じたり、株主間でトラブルになったりする可能性があります。自社株を取得した親族が外部に株を売却すれば、経営に与える影響ははかりしれません。
事前の合意手続きによって自社株を集中できれば、後継者としても安心して事業経営に専念できるでしょう。
一方で、除外合意等のデメリットは手続きに手間がかかる点です。あらかじめすべての推定相続人に合意を取り、複数の書類を集めて手続きを行うため、「本当に必要?」と思う人もいるでしょう。
しかし、人間関係や自社株の状況は変化しうるものです。いざ相続が発生すると、生前は納得していたはずの他の相続人から不満が出て、遺留分侵害額を請求される可能性はゼロではありません。また、自社株の評価額が思いのほか上昇してしまい、遺留分侵害になることもあるでしょう。

後継者が決まっていて、相続人の理解も得られている状況であれば、関係が良好なうちに合意をしておくのも経営戦略の一つです。

遺留分に関する民法の特例に基づく除外合意・固定合意について、よくある疑問を解説します。
A.推定相続人が一人でも拒否すれば、この民法特例は利用できません。
推定相続人が未成年者であったり、合意の内容を十分に理解していなかったりすると、後々揉める要因になります。合意形成は慎重に進めましょう。
A.手続きの目安は3~4か月程度です。

経済産業大臣の確認申請や家庭裁判所の許可申し立てに必要な期間は2~3か月程度です。
ただし、必要書類には「推定相続人全員の合意を確認できる書類」から「先代経営者の生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本」などが含まれます。これらの書類収集に1~2か月程度かかる可能性があるため、すべてあわせて3~4か月程度はかかると見込んでおくのがよいでしょう。
A.合意の効力に影響はありません。しかし、新しい推定相続人には要注意です。
除外合意・固定合意は「合意時点の推定相続人」を対象として成立しています。よって、他の推定相続人の合意が(死亡によって)無効になることはありません。
ただし、推定相続人の死亡により、新たに別の推定相続人が出てきた場合は要注意です。新しい推定相続人は元の合意に関与していないため、相続発生時に遺留分を制限することができません。遺留分の額や他の推定相続人との関係性などを考慮し、必要に応じて、再度合意手続きを行いましょう。
京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。