相続専門コラム
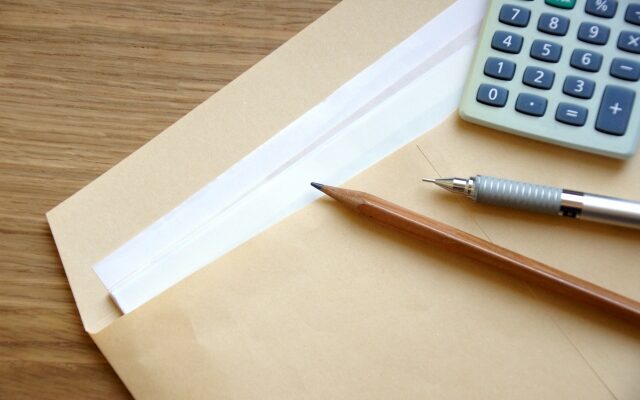
相続税申告は自分で済ませることができます。ここでは相続税申告書を作成する際に必要な書類と、その入手方法について紹介していきます。
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。
相続税申告はすべての方が対象ではありません。遺産の合計額が相続税の基礎控除を超えた場合に申告をしなければなりません。言い換えれば遺産総額が基礎控除以下であれば申告は不要です。
基礎控除は法定相続人の数によって変わります。基礎控除の計算方法は次のとおりです。
【計算式】 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万×法定相続人の人数)
相続税申告時に必要な書類は次のとおりです。ここに記載がない財産で疑問がある方や書類に不安のある方はお近くの税務署、税理士に相談することをおすすめします。
| 必要書類 | 取得場所 |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 市区町村の役所 |
| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村の役所 |
| 被相続人の死亡診断書のコピー | 病院 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村の役所 |
| 相続人全員の住民票 | 市区町村の役所 |
| 相続人全員の印鑑証明 | 市区町村の役所 |
| 遺言書もしくは遺産分割協議書 | 遺言書:公証役場 協議書:相続人で作成 |
| 相続人全員のマイナンバー確認書類 (マイナンバーカード、通知カードの写し) | 各自で準備 |
| 相続人全員の身元確認書類 (運転免許書の写し、パスポートの写し、 身体障害者手帳の写し等) | 各自で準備 |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 預金残高証明書 | 各金融機関 |
| 既経過利息計算書 | 各金融機関 |
| 被相続人の過去5年分の通帳のコピー | 手元にあるもの |
| 相続人・家族全員の過去の通帳のコピー | 各自で準備 |
| 手元にある現金 | ー |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 法務局 |
| 地積測量図及び公図の写し | 法務局 |
| 固定資産税評価証明書 | 市町村の役所 |
| 住宅地図、公図、実測図等 | インターネットサイト等 |
| 名寄帳 | 不動産のある市町村の役所 |
| 賃貸借契約書 (貸家、貸地、借地の場合) | 手元にあるもの |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 証券会社の預かり証明書 | 証券会社や信託銀行 |
| 配当金の支払通知書 | 手元にあるもの |
| 登録証明書(残高証明書) | 証券会社や信託銀行 |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 支払通知書 | 各生命保険会社や勤務先等 |
| 保険証書のコピー | 手元にあるもの |
| 解約返戻金の分かる資料 | 保険代理店契約の生命保険会 |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 自動車の車検証のコピー (車種、色、走行距離等) | 手元にあるもの |
| 電話加入権 (電話番号と所在地) | ー |
| ゴルフ会員権・リゾート会員権の会員証 | 手元にあるもの |
| 未収家賃・給与・貸付金がわかる証明 | 手元にあるもの |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 金銭消費貸借契約書のコピー (借入金がある場合) | 手元にあるもの |
| 借入残高証明書 (借入金がある場合) | 各金融機関 |
| 債務に関する請求書 | 手元にあるもの |
| 課税通知書・納付依頼書 | 手元にあるもの |
| その他債務がわかる明細・証書 | 手元にあるもの |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 葬儀費用がわかる請求書・領収書 | 手元にあるもの |
| その他葬儀費用がわかるメモ書き、明細書 | 各金融機関 |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 相続時精算課税制度選択届出書 | 手元にあるもの |
| 贈与税申告書 | 手元にあるもの |
| 贈与契約書 | 手元にあるもの |
| 被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの) | 手元にあるもの |
| 必要書類 | 取得場所 |
| 贈与税申告書 | 手元にあるもの |
| 贈与契約書 | 手元にあるもの |
| 贈与したものがわかる書類 (預金通帳等) | 手元にあるもの |
忙しくて市役所や金融機関へ出向く時間がない方は司法書士へ依頼することをおすすめします。司法書士は業務に付随する目的であれば職権を利用して戸籍謄本等の資料収集を行うことができる為、相続人が取得する場合と比較してもスムーズです。
また、経験豊富な税理士、司法書士であれば必要書類の把握もできているため、無駄がありません。
みなと相続コンシェルでは税理士、司法書士が連携しお客様家族の相続税申告をサポートいたします。
【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】
みなとの相続税申告への考え方
みなとの司法書士ご紹介
必要な書類、資料を収集した後は遺産分割を行い、相続税申告書の作成を進めます。
相続税申告書は国税庁のウェブサイトよりダウンロードできます。申告書を作成し、納付すべき税額を算出します。作成した申告書と収集した書類を併せて税務署へ提出し納税をします。
国税庁|相続税申告のしかた(令和元年分用)
国税庁|相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)

みなと相続コンシェルでは誰でも簡単に相続税申告書の作成ができる「AIによるサポートで申告書作成ができる!AI相続」を開発・運営しています。
フォームに従って相続人や相続財産情報等を入力するだけでプログラムが自動で計算、転記し税務署に提出可能な申告書が無料で作成・印刷できます。
申告書を入手、手書きする必要はありません。
【無料で試してみたい方はこちら!】
完全無料!AIによるサポートで申告書が作成できる「AI相続」
相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。