相続専門コラム
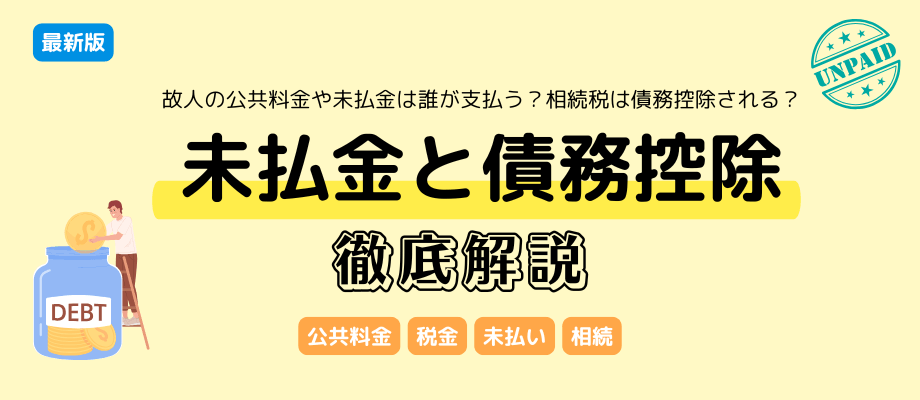
「被相続人の公共料金が未払いの場合、誰が支払うべきなのだろうか?」「未払い分は相続財産から債務控除できるって本当?」こうした疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、故人の公共料金など未払金の支払い義務、医療費に関する軽減措置、遺産分割協議を行う前に支払いが発生する場合の対処方法、債務控除の対象となる債務 / ならない債務、適用条件や計算方法、注意点まで分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読むことで、相続手続きにおける未払金の取扱いと債務控除について必要な知識を蓄える為の一助となれば幸いです。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

相続では基本的にプラスの財産もマイナスの財産(債務等)も引き継ぎます。よって、相続人は故人の死亡時点で発生していた公共料金等の未払い金を支払う義務があります。
これらの支払いを円滑に進めるためには、まずは故人が契約していたサービスや支払い方法を把握し、各事業者に連絡して必要な手続きを行うことが重要です。
支払いの種類と対応手続き
| 支払いの種類 | 具体例 | 手続き方法 |
|---|---|---|
| 公共料金 | 電気、水道、ガス、ケーブルテレビ、NHKなど | 各社に死亡を通知し、解約や名義変更を行って未払い料金を精算する |
| 電話・ネット回線 | 携帯電話、インターネットプロバイダー、固定電話など | 各社のお客様窓口に連絡する。書面や店頭での手続きが必要な場合もある |
| クレジットカード | VISA、JCBなど | 通帳明細や財布を確認し、契約中のカード会社に連絡して死亡の手続きを行う |
| 会員カード | デパート友の会など | 運営元に連絡して死亡の手続きを行う。未使用の積立金は解約時に返還される |
| 月会費 | スポーツクラブ、習い事、趣味の集まり、定期購入など | クレジットカード払いや口座引落しの会費や定期購入は、早急に連絡して契約を停止する |
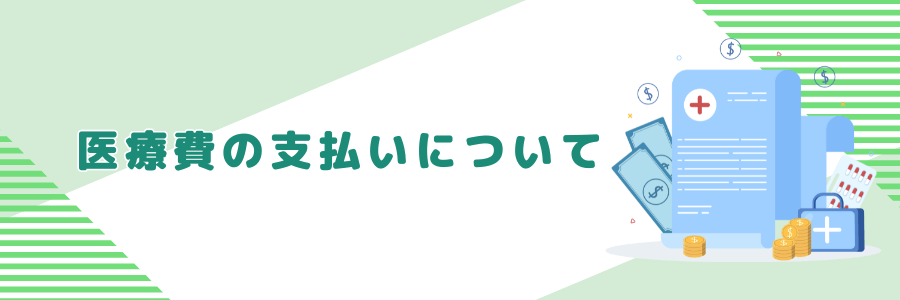
債務を引き継ぐため、相続人は故人の死亡時点で発生していた医療費を支払う義務があります。
なお、医療費の支払いに関しては、高額療養費制度による還付請求や相続人自身の確定申告での医療費控除など、軽減措置を活用できる可能性があります。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が高額になった場合に、一定額を超えた部分が後から払い戻される制度です。
故人の場合も、相続人が高額療養費の支給申請を行うことができます。申請は故人が加入していた健康保険の保険者(健康保険組合や市区町村の国民健康保険など)に対して行います。
相続人が故人の医療費を支払った場合、その医療費を相続人自身の確定申告で医療費控除として申告することができます。なお、医療費控除の対象となる金額は、最高で200万円までとなります。
医療費控除の対象となる金額 = その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い方の金額
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いを行い、相続財産の分配方法を決定する手続きのことです。相続開始後、相続人間で遺産の分け方について合意を形成し、その内容を書面(遺産分割協議書)にまとめることで正式に効力が発生します。
公共料金や医療費等の未払金も相続財産の一部となるため、遺産分割協議において相続人全員で各債務の負担者や精算方法を取り決める必要があります。
しかし、遺産分割協議が完了する前でも、被相続人の公共料金や医療費などの未払金については支払期限に合わせて対応する必要が出てきます。
このような場合、相続人の代表者が一時的に立て替えて支払うことが一般的です。その際、後日の精算のために支払った金額や内容を記録し、領収書などの証明書類をしっかりと保管しておくことが重要となります。
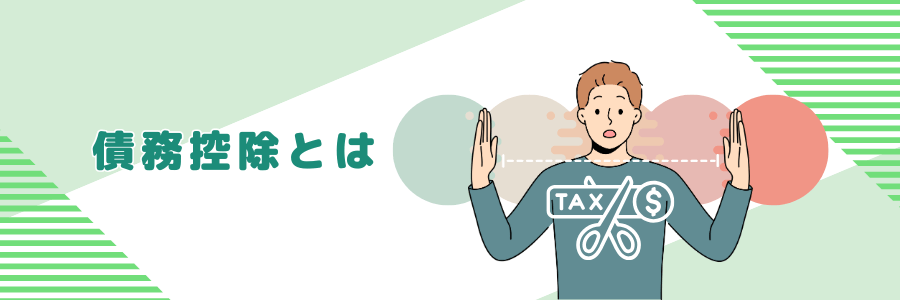
債務は相続によって引き継ぐ事になる一方で相続税の申告時にはメリットもあります。それが債務控除です。債務控除とは、相続財産から被相続人に帰属する債務を差し引くことができる制度です。
債務は相続税の計算で相続財産から控除することができ、課税対象額を減らせます。これにより、故人の債務を引き継いだ相続人の負担が軽減されます。
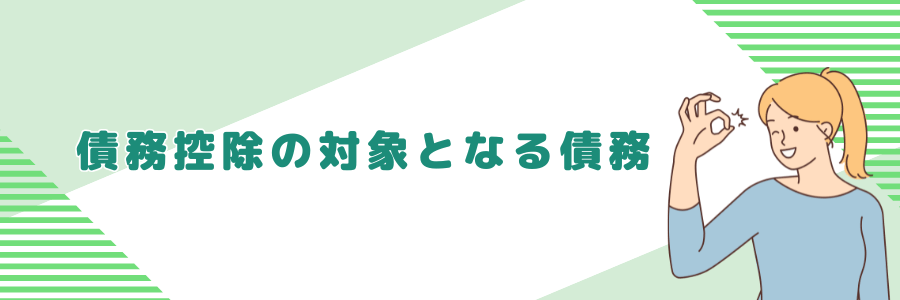
債務控除の対象となる項目は多岐にわたります。しっかり漏れなく確認しておきましょう。なお、債務控除を適用するためには、債務の存在を証明する書類が必要となりますのでご注意ください。
もし必要書類の添付や未払金の支払いを忘れた場合、債務控除を受けることはできません。
債務控除の適用をスムーズに進めるために、故人の債務に関する書類(住宅ローンの契約書、医療費の領収書、公共料金の請求書など)を整理・保管しておきましょう。
借入金は債務控除の代表的な対象項目です。以下の表に主な借入金の種類と注意事項をまとめました。
| 借入金の種類 | 具体例 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 銀行からの借入金 | 住宅ローンや事業用借入金、カードローンなど | 連帯債務がある場合、被相続人が負担していた割合分については債務控除の対象となる。 |
| その他個人からの借入金 | 親族や知人からの借入金など | 口約束による借入は債務控除の対象として認められないことがある。個人間の借入金については、金銭消費貸借契約書等の書面を用意しておく。また、貸付時の資金の流れを証明できる預金通帳のコピー等も用意することが望ましい。 |
未払金は、故人の死亡時点で支払義務が発生していた債務のことを指します。以下の表に、主な未払金の種類とその注意事項についてまとめました。なお、死亡後に発生したものについては対象外です。
| 未払金の種類 | 具体例 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 公共料金 | 電気・ガス・水道など | 月途中の死亡の場合、生存日数に応じた日割り計算で算出した金額を控除できる。 |
| 医療費 | 入院費、手術費、投薬費用など | |
| 固定資産税 | 死亡時点で未払いの固定資産税 | 例えば、前年12月分まで支払済みで1月に死亡した場合、1月分と翌年度分が債務控除の対象となる。 |
| 所得税 | 死亡時点で未払いの所得税 | 準確定申告で納付する所得税は債務控除の対象となる。ただし、還付される場合は相続財産に計上する。 |
| 住民税 | 死亡時点で未払いの住民税 | 住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、死亡年度の住民税についても、死亡時点までの期間に対応する税額は債務控除の対象となる。 |
| クレジットカードの未払金 | クレジットカードの利用料 | |
| 延滞金・督促手数料 | 税金や公共料金の延滞金、督促手数料など | 被相続人が生前、納付することを忘れていて課されたものに限る。 |
| 介護費用の未払金 | 介護サービス利用料など | |
| 事業上の未払金 | 仕入先への買掛金、従業員への給与、業務委託費用など | |
| 預かり敷金 | 賃貸物件のオーナー(被相続人)が入居者から預かっている敷金 | 入居者との賃貸借契約に基づいて返還義務が生じる。 |
| 求償不能の保証債務 | 故人が他人の借金などの保証人となっていた場合の債務 | 主たる債務者から返済を受けることができない場合、相続人が実質的に負担することになるため、債務控除の対象として認められる。 |
| 共有不動産に関する債務 | 修繕費用や固定資産税など | 故人の持分に応じた金額が債務控除の対象となる。共有者間で費用負担の取り決めがある場合は、その取り決めに基づいた金額が控除対象となる。 |
お通夜の式場費用、告別式の飲食費、祭壇や供花の費用、僧侶への謝礼、戒名料、火葬料、遺体の搬送費用、死亡診断書の発行費用等の葬式費用については、実際に支払った金額が控除対象です。
ただし、香典返しの費用や法事の費用など、葬儀に直接必要でない費用は控除対象外となります。
※参考:国税庁 | 相続財産から控除できる葬式費用
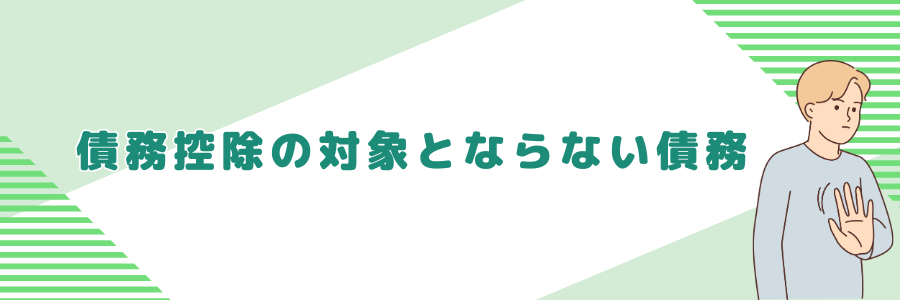
相続税の債務控除の対象とならないものについて、以下の表にまとめました。これらは相続税の計算上、控除することができません。
| 対象外となる理由 | |
|---|---|
| 団体信用生命保険で補填される住宅ローン | 団体信用生命保険が付保されている住宅ローンの場合、借入人が死亡した時点で保険金によってローン残高が返済されるため、債務控除の対象外となる。 |
| 保証債務 | 主たる債務者から求償できることが明らかな保証債務は、債務控除の対象外となる。 |
| 延滞税・加算税 | 税務申告の期限を過ぎて納付する場合に発生する延滞税や税務調査により課される加算税は、故人の死亡後に発生したものとみなされるため、債務控除の対象外となる。 |
| 非課税財産に係る未払金 | 非課税財産自体が相続税の課税対象とならないため、墓石の建立費用や仏壇の購入費用など、相続税法上の非課税財産に関連する未払金については債務控除の対象外となる。 |
| 控除できない葬式費用 | 葬儀の実施に直接必要な費用とは認められないもの(香典返しの費用、法事の費用など)は債務控除の対象外となる。 |
| 控除対象にならない医療費 | 本人の希望による差額ベッド代、医療器具ではない物品の購入費などは控除対象外。健康保険などから給付される医療費や生命保険から支払われる入院給付金などで補填される部分についても、債務控除の対象外となる。 |
| 故人の死亡後に発生する費用 | 故人の死亡後に発生する費用は、原則として債務控除の対象外。これには解約金を振り込む際の振込手数料、死後の不動産管理費用、相続手続きに関する費用、相続税の納付に関連する費用などが含まれる。 |
また、以下のような場合も債務控除を利用することができません。
相続を放棄した人は、相続人としての権利を放棄したことにより、相続財産に対する権利も義務も一切引き継がないことになります。
そのため、相続放棄した場合は債務控除を利用する資格も失うことになります。
日常家事債務とは、日用品の購入や医療費、公共料金など、日常生活に必要な債務のことを指します。
日常家事債務は生活を共にする者が連帯して支払い責任を負います。したがって、相続を放棄した場合でも、被相続人と同居していた相続人は日常家事債務の支払い義務を免れることはできません。これは民法第761条に基づく規定であり、生活の実態に即した責任の分担を定めたものです。
制限納税義務者とは、日本に住んでいる期間が短い人や海外に住んでいる外国人のことです。納税義務は「日本国内の遺産」に対してのみ発生します。
そのため、借金や未払い費用の控除も「日本国内の財産に関係するもの」だけに認められます。つまり、「海外の財産に関する負債」や「相続人自身が負担した葬儀費用」は控除の対象外となります。
特定受遺者とは、遺言によって特定の財産のみを受け取る人のことを指します。
特定受遺者は、債務控除の対象とはなりません。ただし、包括受遺者(財産の指定なしで相続割合のみ指定された受遺者)の場合は、債務控除の対象となります。
また、以下の場合は相続税申告自体が不要となるため、債務控除を適用する必要がありません。
相続財産が基礎控除額以下の場合は、債務控除の適用を検討する必要はありません。これは、相続税の申告自体が不要となるためです。
相続財産の評価額から債務を控除した金額が基礎控除額以下になる場合、相続税の申告は不要となります。ただし、債務控除の計算は正確に行い、その根拠となる必要書類は保管しておきましょう。
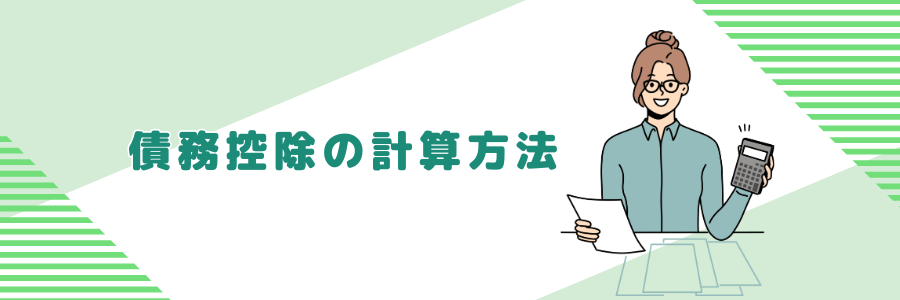
債務控除を適用する場合、遺産総額から基礎控除とともに控除できます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人
例えば、以下のような相続財産と債務があった場合を考えてみましょう。法定相続人は2人とします。
合計:1億5,000万円
合計:3,530万円
合計:4,200万円
1億5,000万円 - 3,530万円 - 4,200万円 = 7,270万円
(相続財産総額 – 債務控除額 – 基礎控除額 = 課税対象となる相続財産)
上記の例では、債務控除を適用しない場合の課税対象は、相続財産1億5,000万円から基礎控除額4,200万円を差し引いた1億800万円となります。しかし、債務控除を適用することで、相続税の課税対象となる相続財産を7,270万円まで圧縮することができます。
このように、債務控除を適用することで、相続税の課税対象となる財産を減らすことが可能です。なお、借金や未払金は全額控除可能ですが、光熱費については日割りで計算します。
電気・ガス・水道など、光熱費の日割り計算が必要な場合は、各契約会社に確認して正確な数字を入手しましょう。計算について不安がある場合は税理士に相談することをお勧めします。
月額料金 ÷ 検針期間日数 × 使用日数
例えば、月額料金8,000円の電気料金について、検針日が毎月20日で故人が15日に亡くなった場合。
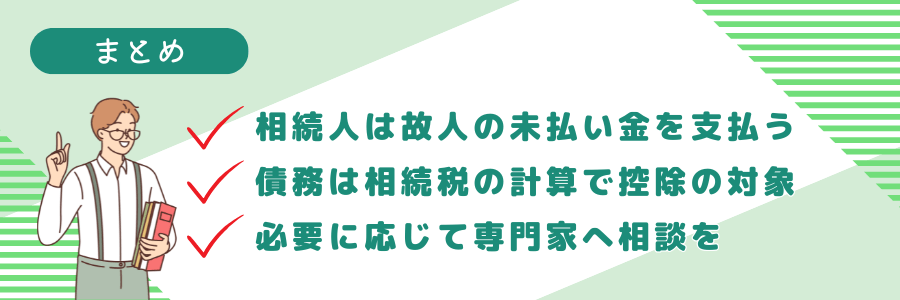
本記事では、故人の公共料金や未払金の支払い義務、相続税における債務控除の適用条件と計算方法について解説してきました。
相続人は故人の未払い金を支払う義務があり、これらの債務は相続税の計算において控除の対象となります。適切な証明書類の準備と債務控除の計算が重要となるため、必要に応じて専門家への相談をお勧めします。
ご不明な点があればお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。
【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】
東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室