相続専門コラム
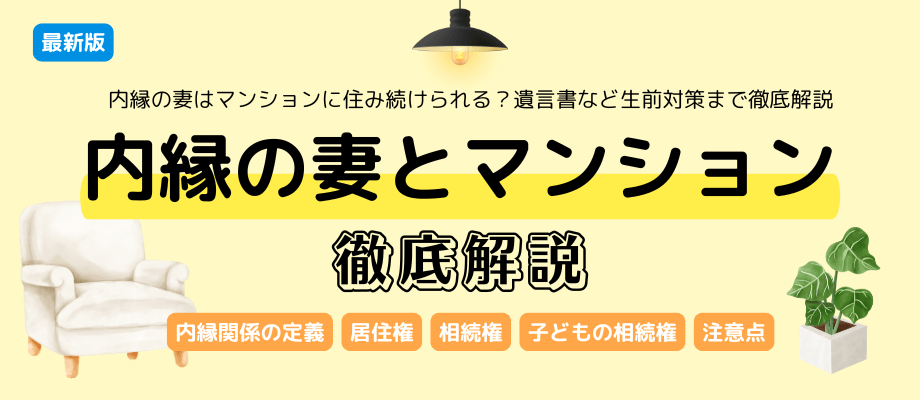
「内縁の妻は夫の死後に今住んでいるマンションを追い出されるのかな?」「内縁の妻が遺産を相続できる方法はないの?」「内縁の夫が亡くなった後でも行える対策はある?」こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、内縁関係の定義、内縁の妻(夫)に居住権はあるのか、内縁の妻との子どもに相続権はあるのか、内縁の妻が遺産を受け取る方法、内縁の妻が遺産を受け取った場合の注意点まで分かりやすく解説します。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。
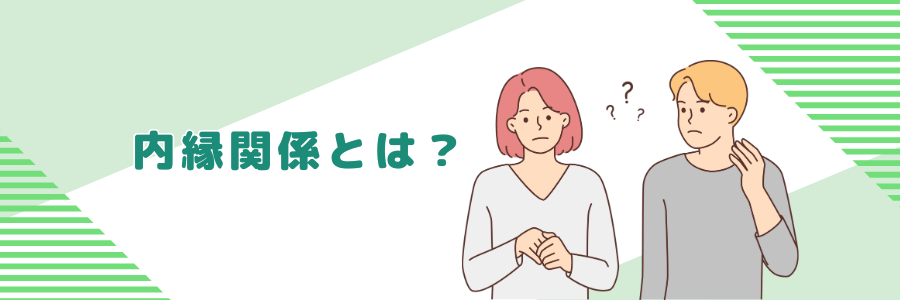
内縁関係とは、婚姻届を提出していないものの、事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。法律上の婚姻関係とは異なりますが、社会的には夫婦としての実態を持つ関係性です。この関係が成立するには、当事者間に婚姻の意思があり、かつ社会的に夫婦として認められる共同生活を営んでいることが必要です。
内縁関係にある女性は「内縁の妻」、男性は「内縁の夫」と呼ばれ、法律婚に準じた保護を一定範囲で受けることができます。婚姻費用の分担や同居の義務が生じるほか、不当な解消や不貞行為があった場合は慰謝料の対象となります。また、二人で築いた財産は財産分与の対象となります。
「内縁の妻(夫)」の定義については、以下の記事で詳しく解説しています。
内縁の妻や子に相続権はある?遺産を受け取るための方法【徹底解説】
法律上の配偶者は、婚姻届を提出して正式に婚姻関係を結んだ夫婦を指します。内縁の妻(夫)は、婚姻届は提出していないものの、事実上の夫婦として認められる関係にある人を指します。一方、愛人は、法的にも社会的にも夫婦としての実態がない不倫関係にある人を指し、法的保護の対象とはなりません。
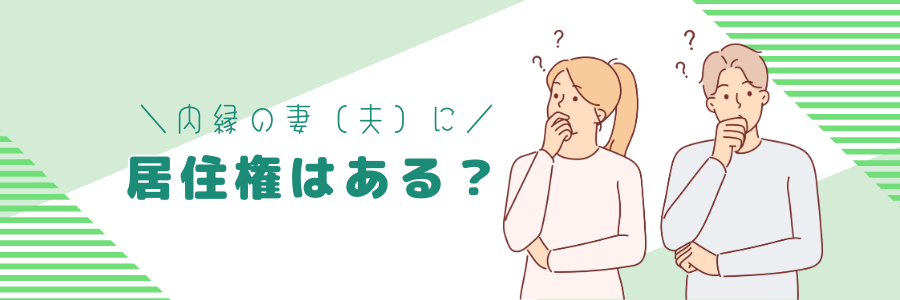
内縁の妻(夫)の居住権については、一定の保護が認められる可能性があります。
ただし、内縁の妻(夫)には法定相続人としての相続権はありません。これは、婚姻届を提出していない以上、法律上の配偶者とは認められないためです。また、内縁の妻は法律上の配偶者ではないため、配偶者居住権(被相続人所有の建物に無償で住み続けられる権利)や配偶者短期居住権(相続開始から最低6か月間住み続けられる権利)も認められません。
内縁の妻は夫と共に財産を築いてきたため、遺産に対する権利があるように思えますが、離婚時とは異なり、過去の判例では死亡時の財産分与は認められていません。そのため、内縁の夫が亡くなった場合、内縁の妻には相続権も財産分与権もないのです。
内縁の妻は法定相続人ではないため、マンションの相続権は認められませんが、居住権の保護は認められる可能性があります。
具体的には、内縁の妻が長年にわたって共同生活を送っていた場合や、経済的な依存関係が強い場合には、相続人からの立退き請求が権利の濫用とされる可能性があります。過去の判例では、相続人の居住の必要性と内縁の妻の事情を秤にかけて判断されています。
最高裁昭和39年10月13日判決では、相続人に差し迫った使用の必要性がなく、内縁の妻側に経済的打撃が大きいことから、立退き請求は権利の濫用として認められませんでした。また、大阪高裁平成22年10月21日判決では、内縁の妻が死亡するまでの使用貸借契約が黙示的に成立していたとして、相続人からの立退き要求を認めませんでした。
賃貸物件に居住していた場合、契約者の死亡後は賃借権(アパートに住む権利)が相続人に継承されます。内縁関係の場合は賃借権を相続できないため、家主から退去を求められた場合は原則として応じる必要があります。逆に言えば、家主の判断によって内縁の妻の継続居住が認められる可能性もあります。
それでは、家主から居住を許可されても相続人が賃借権を主張してきた場合はどうなるでしょうか。相続人に差し迫った使用の必要性がなく、内縁の妻(夫)が退去によって経済的な打撃を受ける場合、明渡請求は権利の濫用とされ、認められないケースがほとんどです。したがって、家主の了承があれば、内縁の妻(夫)は新たな賃貸借契約を結んで居住を継続できます。
また、借地借家法では特例として、相続人が存在しない場合に限り、事実上の夫婦関係にあった同居者が賃借権と賃料支払い義務を引き継ぐことができます。
共同購入の場合、内縁の妻(夫)の持分については明確に権利が認められます。つまり、マンションを共同で購入していた場合、内縁の妻(夫)の持分については相続の対象とはならず、その部分の所有権は引き続き保持されます。亡くなった相手の持分については相続人に引き継がれることになりますが、共有不動産の使用料については過去に以下のような判決が出ています。
最高裁平成10年2月26日判決によれば、内縁の夫婦が共有不動産を共に使用していた場合、特別な事情がない限り、一方が死亡した後も他方が単独で使用を継続できるとされています。つまり、内縁の夫婦のどちらか一方の単独所有ではなく、夫婦で共有していた不動産の場合、内縁の夫婦であっても相続人に対して使用料を支払う必要がない可能性があります。
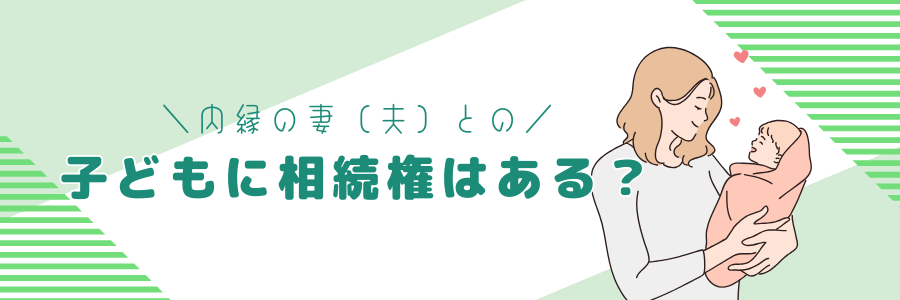
内縁の妻(夫)との間に生まれた子どもは、父親による認知があれば法定相続人として相続権が認められます。遺言による認知も有効です。また、養子縁組をしていた場合は実子と同様の相続権が発生します。
なお、父親が認知せずに亡くなった場合でも、子どもや内縁の妻は父親の死後3年以内であれば認知請求の裁判を起こすことができ、認められれば相続権を得ることが可能です。
内縁の妻(夫)との子どもに関する相続権については、以下の記事で詳しく解説しています。
内縁の妻や子に相続権はある?遺産を受け取るための方法【徹底解説】

亡くなった後に内縁の妻(夫)が遺産を受け取るための手段は限られていますが、内縁の夫(妻)は生前に対策を講じることで遺産を残すことができます。具体的には、条件と合致すれば「特別縁故者の手続き」を行う方法があり、生前対策としては「生前贈与」「生命保険の受取人指定」「遺言書による遺贈」「婚姻関係の締結」などの選択肢があります。
「特別縁故者の手続き」は、法定相続人が不在の場合(または相続人全員が相続放棄した場合)に限り申請できます。この場合、被相続人との特別な関係性を証明する必要があります。
また、「生前贈与」「生命保険の受取人指定」「遺言書による遺贈」を行う際は、法定相続人に保証された最低限の遺産の取り分である「遺留分」に注意が必要です。なお、法定相続人との紛争を防ぐため、「遺言書による遺贈」は公正証書遺言で行うことをお勧めします。
最後に、「婚姻関係の締結」を選択する方法があります。婚姻期間の長さに関係なく、法的な夫婦関係があれば相続権が保証されます。可能であれば、この選択肢も検討に値するでしょう。
内縁の妻(夫)が遺産を受け取る方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
内縁の妻や子に相続権はある?遺産を受け取るための方法【徹底解説】
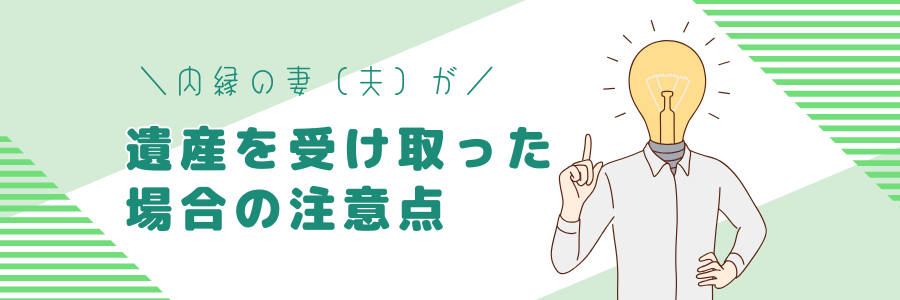
内縁の妻は法律上の配偶者とは異なる扱いを受けるため、相続税の申告において不利な立場に置かれる可能性があります。具体的には、「相続税が2割加算される」「各種控除が受けられない(配偶者控除、障害者控除、小規模宅地の特例など)」が挙げられます。
内縁の妻(夫)が遺産を受け取った際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
内縁の妻や子に相続権はある?遺産を受け取るための方法【徹底解説】
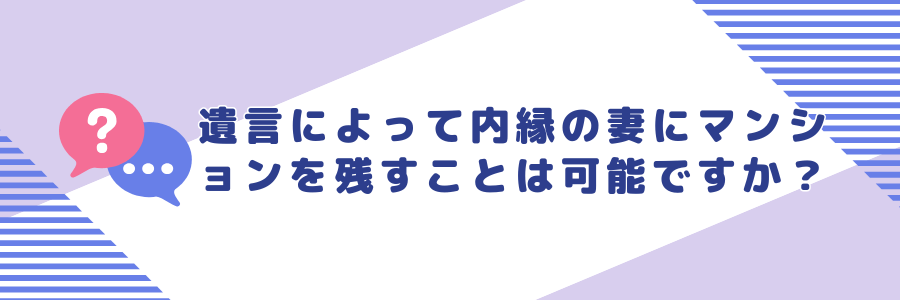
「重婚的内縁」(法律上の配偶者がいる場合の内縁関係)の場合、内縁の妻への遺贈は公序良俗に反するとされ、無効となる可能性があります。
一方、法律上の妻がいない単純な内縁の場合は、遺言によってマンションを内縁の妻に遺贈できます。内縁の妻は相続人ではありませんので、財産取得の法的根拠は「遺贈」となります。
遺贈を確実に実行するためには遺言執行者が必要です。そのため、遺言書にあらかじめ遺言執行者を指定しておきましょう。公正証書遺言であれば確実ですし、検認の必要もないためお勧めです。この際、内縁の妻が必要とする生活費等についても言及しておくと良いでしょう。
ただし、遺言書を作成する際は法定相続人の遺留分(一定の法定相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分のこと)を考慮に入れる必要があります。
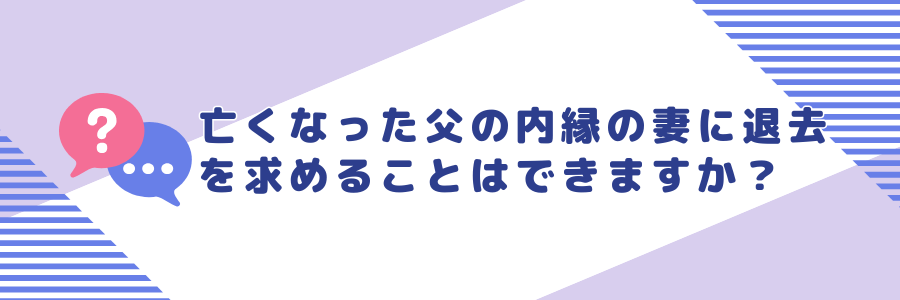
内縁の妻は法定相続人ではなく、マンションの相続権や配偶者居住権もありません。したがって、法律上は立退きを求めることが可能であるように思えます。
しかし、裁判例では、内縁の妻側の経済的打撃や相続人側の必要性などを考慮し、立退き請求を認めないケースもあります。また、被相続人と内縁の妻との間で死後の無償使用について合意があったとして、明渡請求を否定した例もあります。
そのため、相続人は内縁の妻を即座に退去させられるとは限りません。立退きを拒否された場合は、マンションの有償譲渡や賃料支払いについての協議を検討する必要があります。これには内縁の妻の同意が必要ですが、同意がない場合でも「不当利得返還請求(民法第703条、第704条)」や「使用貸借の必要費請求(民法695条)」の適用により請求が可能な場合もあります。
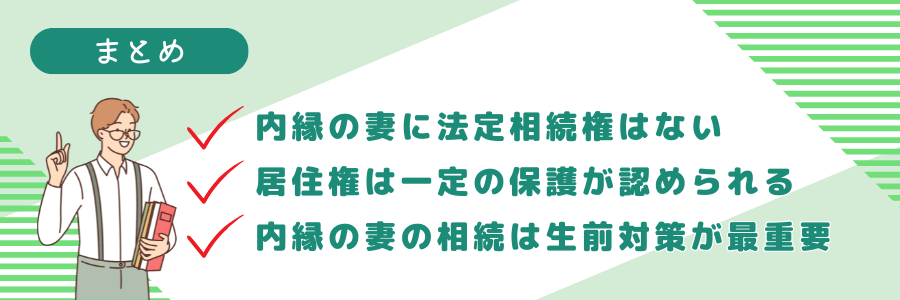
内縁の妻(夫)には法定相続人としての相続権はありません。ただし、居住権については一定の保護が認められる可能性があります。
内縁の夫との間に生まれた子どもについては、認知されている場合は法定相続人として相続権を持ちます。認知がない場合も、父親の死後3年以内であれば認知請求の裁判を起こすことができます。
内縁の妻(夫)が確実に遺産を受け取るためには、婚姻関係を締結するのが最善策です。婚姻期間の長さに関係なく、法的な夫婦関係があれば相続権が保証されます。
事情により婚姻関係を結べない場合、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の活用などの生前対策が重要となります。また、法定相続人が不在または相続放棄した場合は、特別縁故者として裁判所へ申し立てることで、遺産の一部を受け取れる可能性があります。
内縁関係であっても、事前に適切な準備をしておくことで、パートナーの死後に備えることは可能です。もし具体的な対応に迷う場合は、専門家へ相談することをおすすめします。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。
【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】
東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室