相続専門コラム
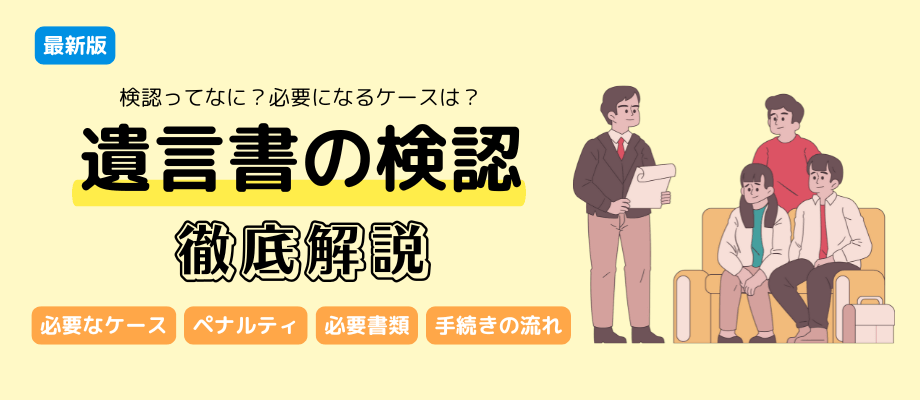
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合、発見者は独断で開封してはいけません。必ず家庭裁判所での「検認」という手続きを先に行う必要があります。
本記事では、「検認とは何なのか?」「どのようなケースで必要なのか?」「なぜ検認が必要なのか?」をご紹介した上で、手続きの流れや必要書類、費用、注意点等について詳しく解説します。
本記事を読み進めることで、遺言書の検認手続きを円滑に行えるようになります。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。
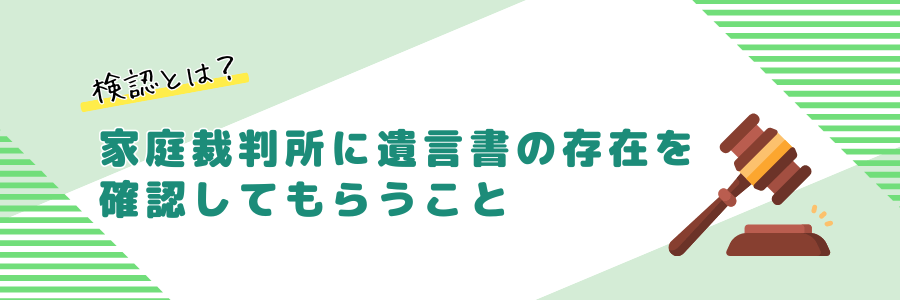
「検認」とは、家庭裁判所に遺言書の存在を確認してもらう手続きです。
裁判所の公式サイトでは、次のように解説されています。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
引用:裁判所「遺言書の検認」
「検認」とは、遺言書の発見時の状態を家庭裁判所が公式に記録し、偽造や変造を防止するための手続きです。遺言書は家庭裁判所でのみ開封が認められており、自宅などでの開封は禁止されています。
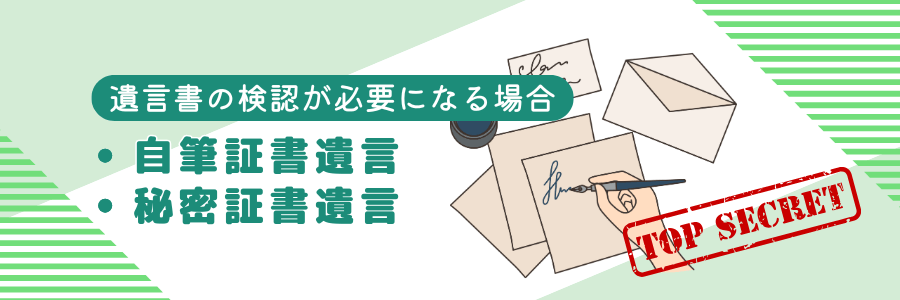
遺言書には、大きく分けて次の2つの方式があります。
普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。一方、特別方式遺言には「一般危急時遺言」(病気や怪我により死亡の危機が迫っている場合に利用可能)や「一般隔絶地遺言」(伝染病による隔離中や刑務所服役中などの場合に利用可能)などがあります。
家庭裁判所の検認が必要なのは「普通方式遺言」のうち、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の2つです。
| 普通方式遺言の種類 | 概要 | 検認 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者自身が作成した遺言書 | 必要 | ただし、法務局の保管制度を利用した場合は検認不要。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言内容を秘密にした遺言書 | 必要 | |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成した遺言書 | 不要 |
遺言者が自ら作成した遺言書のことです。この遺言書は検認が必要となります。ただし、法務局の保管制度を利用した場合は検認は不要です。
遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在を証明してもらう遺言書です。遺言者は作成した遺言書に封をして公証役場へ持参し、内容を秘密にしたまま自身で保管します。この遺言書も検認が必要です。
公証人が法律に基づき作成した遺言書です。公証人が作成するため、改ざんや偽造のリスクがなく、検認の手続きは不要です。
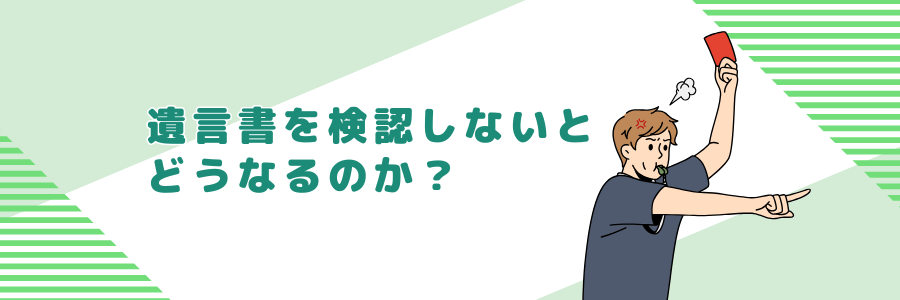
遺言書の検認証明書がない場合、被相続人の銀行口座や証券の名義変更・解約、相続登記等の手続きが行えません。
また、遺言書を検認していなければ、「相続放棄」や「遺留分侵害額請求」の判断もできません。
遺言書の検認に期限の定めはありませんが、各種相続手続きには時効・期限があります。遺言書を検認せずに放置すると、相続放棄や遺留分侵害額請求ができなくなる、相続税申告の期限に間に合わなくなるなどの問題が発生する可能性があります。
| 相続手続き | 時効・期限 |
|---|---|
| 相続放棄 | 相続開始から3カ月 |
| 遺留分侵害額請求 | 相続開始、および遺留分の侵害を知った日から1年 |
| 相続税申告・納付 | 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月 |
遺言書の検認の申し立てから検認期日までは、通常数週間〜1か月ほどかかります。また、申し立てに必要な戸籍謄本類の収集にも1カ月程度を要する場合があります。
そのため、遺言書発見から検認手続き完了までには余裕を持って2~3カ月程度を見込んでおく必要があるでしょう。遺言書を発見したら、速やかに着手することをお勧めします。
検認が必要な遺言書を発見した相続人が、検認を経ずに勝手に開封した場合、5万円以下の過料を科される可能性があります。
そのため、遺言書と思われるものを自宅などで発見した場合は、必ず家庭裁判所での検認を受けてから開封するようにしましょう。
ただし、検認前に誤って開封してしまった場合でも遺言書自体は無効にはなりません。誤って開封してしまった場合は、そのまま破棄せずに速やかに検認の手続きを行いましょう。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
引用元:e-Gov法令検索
遺言書の検認を行わずに勝手に開封してしまうと、他の相続人から遺言書の改ざんを疑われ、相続トラブルに発展する恐れがあります。
誤って遺言書を開封してしまった場合は、トラブルを防ぐために他の相続人に速やかに相談し、検認の手続きを行いましょう。
検認を放置した場合、遺言書を隠匿したとみなされて相続資格を失う可能性があります。そのため、検認が必要なケースでは速やかに手続きを行いましょう。
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
(略)
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:e-Gov法令検索
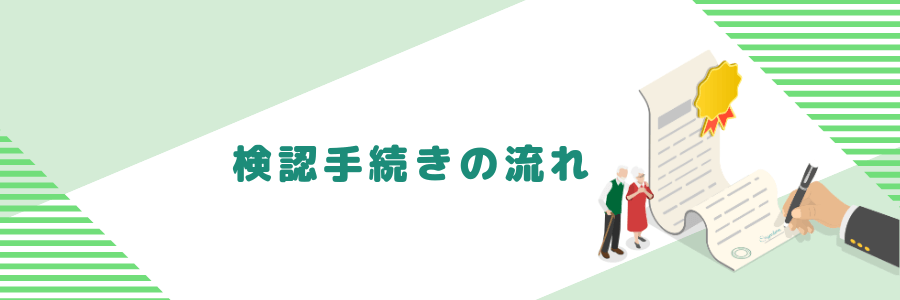
遺言者の死亡後に遺言書を発見した場合は、検認の申立てに必要な書類を準備します。必要書類は以下の通りです。
申立てに必要な書類
第二順位相続人と第三順位相続人の場合は追加で必要となる書類があります。詳しくは裁判所の公式サイトをご覧ください。
なお、申立て前に入手が困難な戸籍がある場合は、申立て後に追加提出することが可能です。ただし、戸籍謄本を代理人が取得する際は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
申立てに必要な費用
また、遺言者の戸籍謄本・除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の取得にも費用が必要です。申立て準備から検認完了までの総費用は、最低でも3,000円程度を見込んでおくとよいでしょう。ただし、これは目安であり、必要な戸籍謄本の件数によって変動します。
補足:戸籍証明書等の広域交付制度
従来、戸籍謄本等の証明書は本籍地の市区町村役所窓口でのみ申請が可能でしたが、2024年3月1日より戸籍情報連携システムが導入され、最寄りの役所窓口で全国の戸籍情報を請求できるようになりました。
書類の準備が完了したら、家庭裁判所に申立てを行います。申立てを行うことができるのは、次のいずれかに該当する人です。
申立人の資格要件
申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。予約等の事前の手続きは不要です。管轄裁判所を調べたい方はこちらをご覧ください。
申立ては郵送または直接持参のいずれかの方法で行えます。書類に不備があると複数回のやり取りが必要となるため、郵送の場合は事前に裁判所へ電話をして不明点を確認しておきましょう。また、必ず追跡可能な郵送方法を選択してください。
戸籍謄本などは提出前に必ずコピーを取っておきましょう。原本とコピーを一緒に提出することで、検認申立て後に原本の返却を受けることができます。戸籍謄本は金融機関での相続手続きなどで必要となるため、検認で使用した原本を返却してもらうことをお勧めします。
提出書類に不備がなければ、申立てから2週間~1カ月後に家庭裁判所から「遺言書検認期日通知書」が郵送され、検認日時が通知されます。
通知書に記載された日時に検認が実施されるため、申立人と相続人は指定された日時に家庭裁判所へ出向く必要があります。
審判期日通知書に記載された日時に、遺言書の確認作業と開封を行う検認が実施されます。
検認当日は申立人の出席が必須ですが、その他の相続人の出席は任意となります。したがって、相続人全員が揃っていなくても検認を実施することができます。
なお、相続人が欠席したとしても、遺言書に記載された遺産の相続ができなくなるなどのデメリットはありません。
検認終了後、相続手続きを進めるために家庭裁判所から検認済証明書を発行してもらいます。
検認を欠席した相続人がいる場合、その相続人には検認済通知書が郵送され、これにより相続人全員に検認完了が通知されます。
検認手続きが完了したら、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきましょう。
遺言書にすべての相続財産が記載されている場合は、その内容に従って不動産の相続登記、金融機関での解約手続き、現金の分割などを行います。
遺言書に記載されていない相続財産がある場合は、その部分について相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を話し合います。
遺言書の効力について争いがある場合は弁護士に相談し、相続税の申告が必要な場合は税理士に相談するなど、必要に応じて専門家のサポートを受けることをお勧めします。
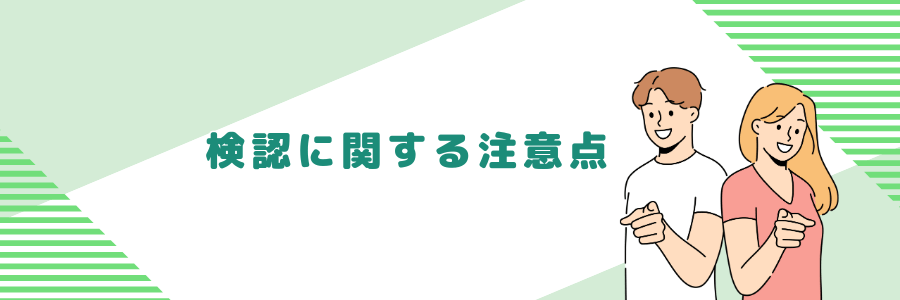
検認は裁判所での手続きのため、遺言書の法的有効性を判断するものだと誤解されがちです。しかし、検認は遺言書の内容が法的に正しいかを判断する手続きではありません。検認の目的は、遺言書の存在を相続人に知らせ、書面の状態を確認することだけです。
遺言書の内容について異議を唱えたい場合、遺言書の効力について争いたい場合等は、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を別途申し立てる必要があります。
家庭裁判所での検認当日には、必ず申立人は出席する必要があります。
なお、検認手続きは裁判所の開庁日である平日のみ実施可能です。土曜日、日曜日、祝日には検認手続きを行うことができません。
検認手続きを一人で行うことに不安がある場合は、弁護士を代理人として立て、同席してもらうことができます。ただし、検認に同席できる代理人は弁護士に限られており、行政書士、司法書士、税理士などの他の専門家は同席できません。
遺言書が複数存在する場合、それらすべてについて検認が必要です。これは検認が遺言の有効性を判断する手続きではなく、遺言書の存在と内容を確認する手続きであるためです。
複数の遺言書が見つかった場合、どの遺言書が法的効力を持つかは検認とは別の問題となり、最終的には裁判での判断が必要となります。
遺言書の検認が行われなかった場合でも、遺言の内容が無効になるわけではありません。
また、遺言の内容を確認し、検認をしないまま遺産分割協議を行うことも可能です。相続人全員が合意すれば、遺言内容とは異なる遺産分割をすることもできます。
ただし、遺言書に従って相続を進める場合や相続人全員の合意が得られない場合は、検認を行わないと前述したようなリスクが生じます。遺産分割をスムーズに進めるためにも、被相続人の死後、なるべく早めに必要書類を集め、検認を行うことをお勧めします。
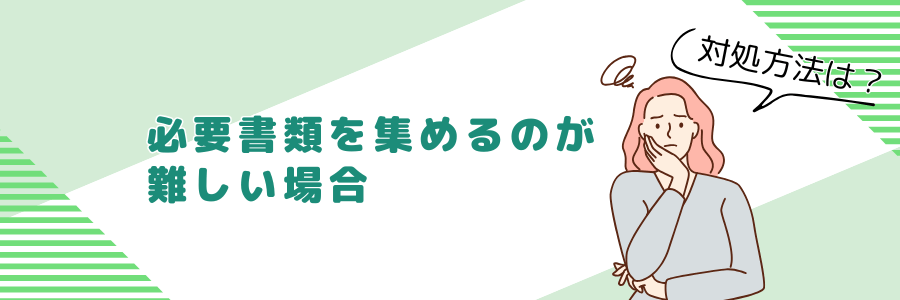
市役所への訪問時間が取れない方には、司法書士への依頼がお勧めです。司法書士は業務目的であれば職権により戸籍謄本などの資料を収集できるため、相続人が自身で取得するよりもスムーズに進められます。
節税を考慮した遺言書の作成をお考えの場合は、税理士への相談が最適です。生前贈与の金額や遺産分割方法による節税効果をシミュレーションしながら、遺言書作成のサポートを行ってくれます。相続財産が基礎控除を超える場合(相続税申告が必要な場合)にも、税理士への相談がおすすめです。
経験豊富な税理士・司法書士は必要書類を熟知しているため、効率的に手続きを進めることができます。みなと相続コンシェルでは、税理士と司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。
【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】
東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室