相続専門コラム
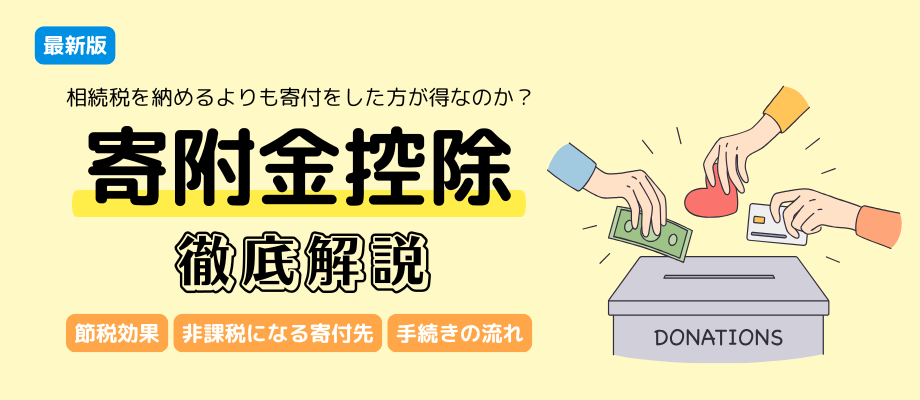
相続財産を受け取った方やこれから相続する予定の方の中には、「相続税を納めるよりも寄付をした方が得なのだろうか?」と考えている方も多いでしょう。
相続財産を非営利団体や国・地方自治体へ寄付することで、相続税の非課税措置、所得税・住民税の控除などの税制上の特例を受けることができ、寄付を通じて社会課題の解決にも貢献できます。
ただし、寄付をすることで実質的な相続財産自体が減少するため、相続財産の金額をできるだけ多く確保したいという目的での寄付はお勧めできません。
本記事では、寄付金控除の概要・メリット・デメリット・適用条件・手続きの流れについてわかりやすく解説します。さらに、控除を活用する際の注意点や具体的な計算例もご紹介いたしますので、ぜひご活用ください。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。
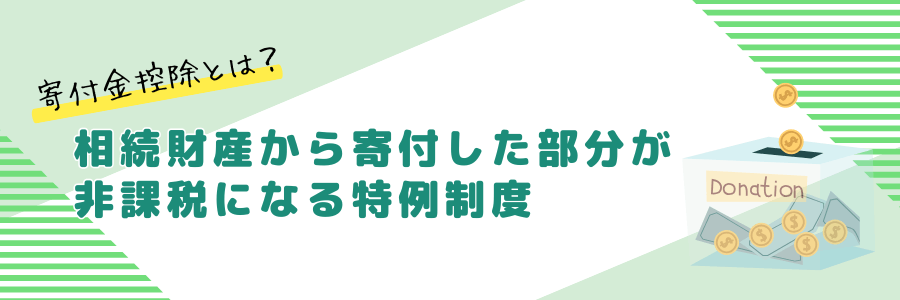
「寄付金控除」とは、相続した財産のうち寄付した部分を相続税の課税対象から除外する特例制度です。非課税の特例を受けられるのは、相続または遺贈で取得した財産を寄付したときです。また、特例の対象となる財産には生命保険金や退職手当金も含まれます。
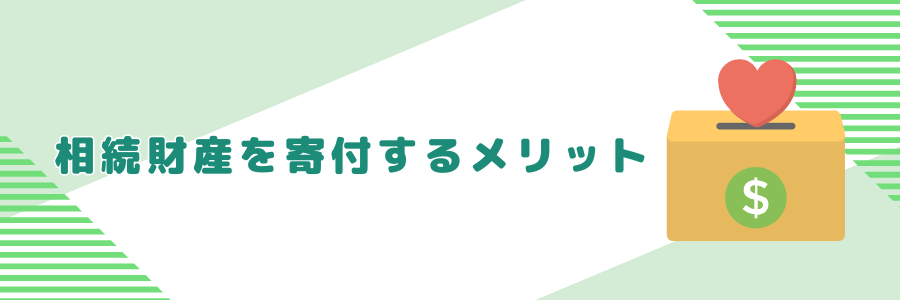
国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人に対して、相続税の申告期限までに寄付をすると、寄付した金額分について相続税が非課税となります。
相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国・地方公共団体・公益を目的とする事業を行う特定の法人、あるいは認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄付した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
引用元:国税庁
相続税の非課税措置は、以下で解説する「寄付金控除」と合わせて適用することが可能です。
相続財産を国や地方公共団体、あるいは特定の公益法人に寄付した場合、相続人は所得税の確定申告で寄付金控除を受けることができます。
寄付金控除は、国や地方公共団体、あるいは特定公益増進法人への寄付金を所得税から控除できる制度です。この控除を受けるためには確定申告が必要です。必ず期限内に申告を行いましょう。
相続した財産を国や地方自治体、特定の公益法人等に寄付した場合、住民税の控除を受けることができます。この場合も所得税と同様、相続人自身が寄付を行い、確定申告をする必要があります。
住民税の寄付金控除には「基礎控除」と「特例控除」の2種類があります。特例控除の対象となるのは、総務大臣が指定する地方自治体(都道府県・市区町村)への寄付のみです。
一方、特定の公益法人や認定NPO法人などへの寄付については、特例控除は適用されません。
故人の生前の関心や大切にしていた価値観に基づいた寄付を行うことで、その方の思いを具体的な形で社会貢献に活かすことができます。
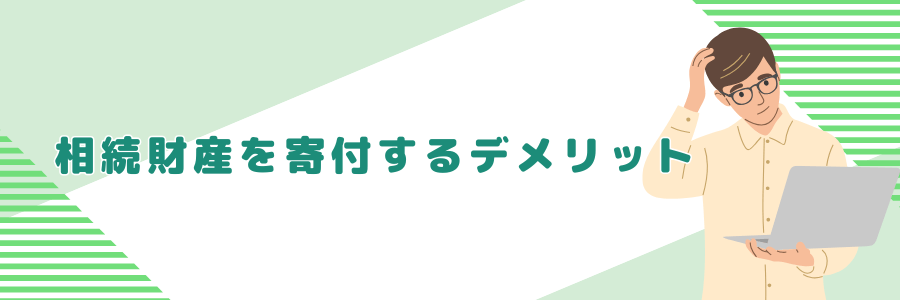
たしかに相続財産を寄付することで相続税は軽減されますが、寄付した分だけ実質的な相続財産も減少することになります。これは相続財産の寄付によるデメリットと言えるでしょう。
そのため、相続財産の金額をできるだけ多く確保したいという目的での寄付はお勧めできません。
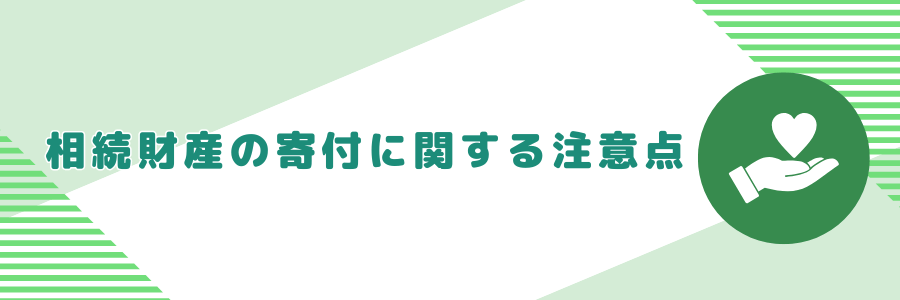
相続税対策として寄付金控除が注目されていますが、活用前にいくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。想定していたような効果が得られないケースもあるため、事前に制度の内容をしっかり確認しましょう。
非課税措置は寄付した相続財産の部分にのみ適用されます。したがって、相続財産を大幅に減らすことなく相続税を軽減したい場合、寄付控除の効果には限りがあります。
また、寄付者本人や親族が公益法人からの寄付を通じて何らかの利益を受けている場合、相続税の不当な軽減とみなされ、特例の適用から除外されることがあります。
寄付をする場合でも、必要な要件を満たさないと特例の対象外となります。特例の適用を受けるには、まず以下の要件を確認する必要があります。
遺贈とは、遺言により法定相続人以外の人が遺産を相続することです。この特例は相続または遺贈による寄付のみが対象となります。寄付は相続税の申告期限である10カ月以内に行う必要があり、認定された団体や組織への寄付に限って適用されます。
私立・公立の大学、ユニセフや赤十字などは特例の対象となりますが、お寺や神社などの宗教法人は「特定の公益法人」や「認定NPO法人」には該当しないため、相続税の特例の対象外となります。そのため、たとえ長年お世話になったお寺への寄付であっても、寄付金控除を受けることはできません。
さらに、以下の場合も特例の適用対象外となります。
遺言書に遺産の寄付に関する指示が記載されている場合、それは被相続人の意思による寄付とみなされ、特例の対象外となります。寄付金控除や相続税の非課税措置は、相続発生後に相続人が自発的に行った寄付にのみ適用されます。
被相続人(遺産を渡す人)が自分の財産を非営利団体へ寄付したいと考えている場合は、「遺贈寄付」という方法が適しています。
「遺贈寄付」とは、被相続人の財産や相続した遺産の一部またはすべてを、遺言などを通じて国や地方自治体、特定の団体に対して寄付することです。遺贈寄付をした財産は課税対象外となるため、相続税の節税対策として効果的です。
被相続人が「相続財産を寄付してほしい」という希望を持っている場合は、遺贈寄付という選択肢について相談することをお勧めします。
法人に対して不動産や株式などの有価証券を遺贈寄付をする場合は要注意です。遺言書に従って法人に寄付する場合、相続税は原則として課税されません。
ただし、不動産等は取得時より資産価値が上がって含み益が生じている場合があります。このような含み益がある不動産等を遺贈寄付すると、その含み益に対して課税されます。これは「みなし譲渡課税」と呼ばれ、譲渡したものとみなされ、含み益相当分が所得として課税対象となります。
不動産を購入してから長い年月が経過している場合、取得価格が不明になることがあります。このような場合、取得価格は「時価の5%」として計算されます。つまり、単純計算で資産が「20倍に値上がりした」とみなされ、みなし譲渡課税の負担が大きくなります。
みなし譲渡課税の場合、納税義務は受贈者ではなく、遺贈者の相続人が負います。ただし、「特定遺贈(特定の不動産等を遺贈寄付すること)」ではなく、「包括遺贈(寄付する財産の割合のみを指定すること)」の場合は、受贈者が納税義務者となり、相続人の税負担は発生しません。
ただし、包括遺贈にも注意点があります。負債も含めて引き継ぐことになるほか、相続財産のうちどの財産を遺贈寄付の対象とするかについて、リスクやトラブルが生じる可能性があります。
相続税の非課税の特例を受けるためには、相続財産をそのままの形で寄付しなければなりません。相続した有価証券や不動産を売却して現金化してから寄付した場合、特例の対象外となります。
ただし、寄付先によっては現金寄付のみを受け付けている場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
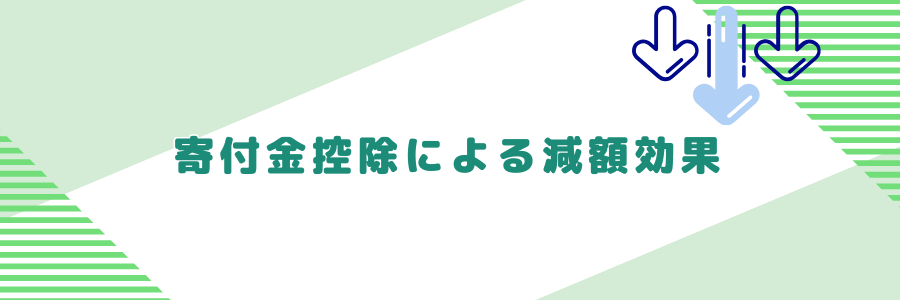
相続財産の寄付のメリットとして相続税が非課税になる点を挙げましたが、非課税となるのは寄付した金額と同額です。
例えば、現金100万円を寄付した場合、その100万円を差し引いた残りの相続財産に対して相続税が課税されます。相続税は10%~55%の超過累進税率が適用されます。
ただし、相続税の課税対象となる金額によっては、相続税を納付した方が手元に残る財産が多くなるケースもあり、必ずしも節税効果が大きいとは限りません。相続財産を寄付する際は、社会貢献や所得税・住民税の控除を受けることを主な目的とすることをお勧めします。
以下が相続税の課税対象額を求める計算式です。
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の税率は、課税の対象となる財産を、法令で定められた割合(法定相続分)に応じて相続人間で分けたと仮定したときの金額によって決まります。例えば、法定相続人が1人の場合、相続財産が3,600万円を超えなければ相続税は発生しません。
多額の相続税が発生する場合で、税金として国に納めることに抵抗がある方は、慈善団体への寄付を通じた社会貢献も一つの選択肢となります。
所得税の寄付金控除額は、次の計算式で求められます。
(寄付した金額-2,000円)×所得税率×1.021(復興特別所得税の税率)
寄付金額から2,000円を差し引いた額に所得税率と1.021を掛けた金額が所得税から減額されます。1.021を掛けるのは、令和19年(2037年)まで所得税額の2.1%を「復興特別所得税」として納める必要があるためです。寄付できる金額は年間総所得の40%まで、控除額は所得税額の25%が上限です。
住民税の減額分は、基本控除額と特例控除額を分けて計算する必要があります。
住民税の税率は自治体によって異なりますが、仮に10%とした場合の基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
(寄付した金額-2,000円)×10%
この計算で算出された金額が住民税から減額されます。ただし、基礎控除の対象となる金額は、総所得金額の30%が上限となります。
住民税率が10%の場合の特例控除額は、次の計算式で求められます。
(寄付した金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
この90%という数値は、100%から住民税率10%を差し引いた値です。なお、特例控除額は総所得額の20%が上限となります。特例控除を受けられるのは、総務大臣が指定する地方自治体(都道府県・市区町村)への寄付に限られます。
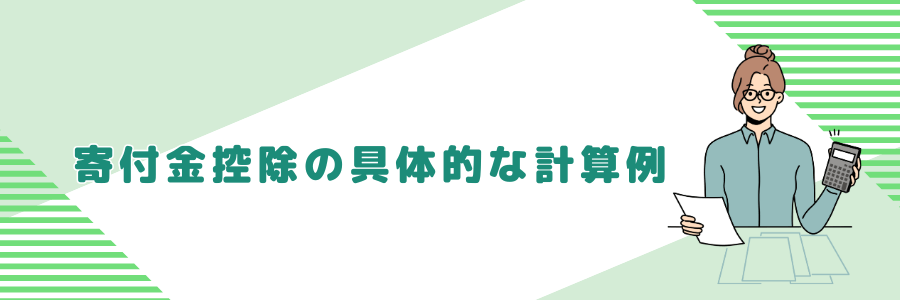
本章では、寄付金控除を活用した場合の節税効果について、具体的な計算例を用いて確認していきます。
まず、法定相続分を計算します。配偶者は1/2で5,000万円、子も1/2の5,000万円となります。
公益法人に5,000万円を寄付したため、課税対象となる相続財産は【遺産総額-相続財産寄付分】の計算式から、【1億円-6,000万円=4,000万円】となります。
次に、基礎控除額を計算します。基礎控除額は【3,000万円+法定相続人の数×600万円】で求められ、今回は【3,000万円+2×600万円=4,200万円】となります。
課税対象となる相続財産の合計額から基礎控除額を差し引いた値がマイナスまたはゼロの場合、相続税は課税されません。今回のケースでは-200万円となり、相続税の負担はありません。ただし、特例の適用には税務署への申告が必要なため、相続税申告書は提出しなければなりません。
また、この場合、相続財産の金額は寄付金額6,000万円を除いた4,000万円になることにも注意が必要です。なお、寄付を行わなかった場合は【1億円-4,200万円=5,800万円】が課税対象となり、今回の場合だと相続税額は385万円です。そのため、手元には1億円-385万円=9,615万円が残ります。
一人当たりの相続額は寄付した場合は2,000万円、寄付しなかった場合は4,807万5千円となります。
ここでは、相続財産の寄付による税負担の軽減効果を具体的な計算例でシミュレーションします。シミュレーションの条件は以下のとおりです。
この条件で、相続財産から50万円を地方自治体に寄付した場合の減税額を見ていきましょう。
相続税の減税額は、寄付金額に相続税率を掛けて計算します。
相続税:寄付金額50万円×相続税率30%=15万円
所得税の減税額は、【寄付金額-2,000円】に所得税率と1.021を掛けて算出します。
所得税:(50万円-2,000円)×40%×1.021=20万3,383円
住民税の基本控除額は、【寄付金額-2,000円】に住民税率を掛けて計算します。
住民税(基本控除額):(50万円-2,000円)×10%=4万9,800円
特例控除額は、【寄付金額-2,000円】に【90%-所得税率×1.021】を掛けて算出します。
住民税(特例控除額):(50万円-2,000円)×(90%-40%×1.021)=24万4,817円
相続税、所得税、住民税の減額分を合計すると以下のようになります。
合計節税額:15万円+20万3,383円+4万9,800円+24万4,817円=648,000円
このシミュレーションにより、地方自治体へ50万円の相続財産を寄付した場合、64万8,000円の節税効果が得られることが分かりました。このように、節税効果は相続人の課税所得に依存します。
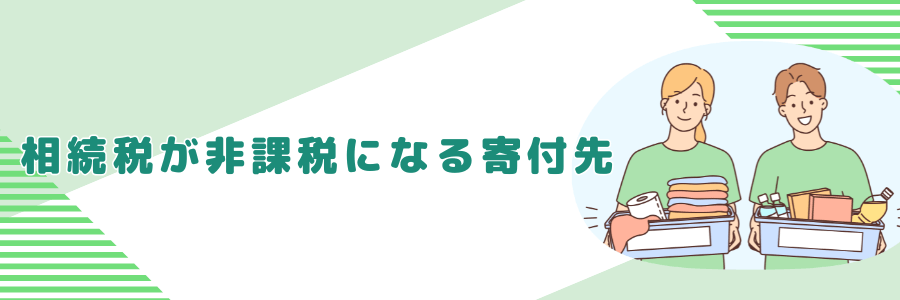
相続税が非課税になる特例は、すべての寄付先に適用されるわけではありません。相続税が非課税となる寄付先は、以下の4つです。また、従来公益信託や公益法人に関しては、寄付に際して国税庁長官の承認が必要でした。2025年の税制改正によって「みなし承認制度」の対象となり申請が簡略化されたため、手続きのハードルは大幅に下がっています。
国や地方自治体(都道府県・市区町村)への寄付は、相続税の非課税の特例の対象となります。また、所得税の寄付金控除や住民税の基本控除も受けられます。
地方自治体への寄付の場合は、住民税の「特例控除」も適用されます。代表的な例として「ふるさと納税」があり、返礼品を受け取ることも可能です。
「公益信託」とは、個人や法人が一定の財産を銀行(信託銀行等)に委託し、その銀行が財産を管理・運用して公益目的に使用する制度です。遺産を公益信託に支出する場合も公益性が高いため、相続税の免除特例が適用されます。
ただし、その公益信託は、教育や科学の振興などへの貢献が著しいと認められるなど、一定の基準を満たすことが証明されている必要があります。
認定NPO法人とは、NPO法人(特定非営利活動法人)のうち、設立年数や寄付実績などの一定の条件を満たした団体のことです。
特定公益増進法人とは、教育や科学の振興などへの貢献が著しいと認められ、公益を目的とする事業を行う特定の法人です。例えば、私立大学・高校などの学校法人や、日本赤十字社、ユニセフなどが特定の公益法人にあたります。
これらの非営利団体についても相続税の非課税の特例の対象となります。
非営利団体の活動内容は各団体によって異なります。相続人が支援したいと考える団体を選んだり、被相続人が生前関心を持っていた活動を行う団体へ寄付したりするのも良い方法です。
寄付先が非課税や寄付金控除の対象となるかどうか判断が難しい場合は、検討している団体へ事前に確認することをお勧めします。ただし、公益法人の設立前の寄付や設立に向けた寄付は非課税の特例の対象外です。また、以下の場合も特例を受けることができません。
2025年の税制改正により、相続税が非課税になる対象として新たに国立健康危機管理研究機構と準学校法人が加わりました。
どちらの場合も、寄付した財産が一定の手続きで基金に組み込まれる場合のみ非課税の特例の対象となります。準学校法人に関しては、学校法人の理事・監事・評議員やそれらの親族など以外からの寄付が対象です。
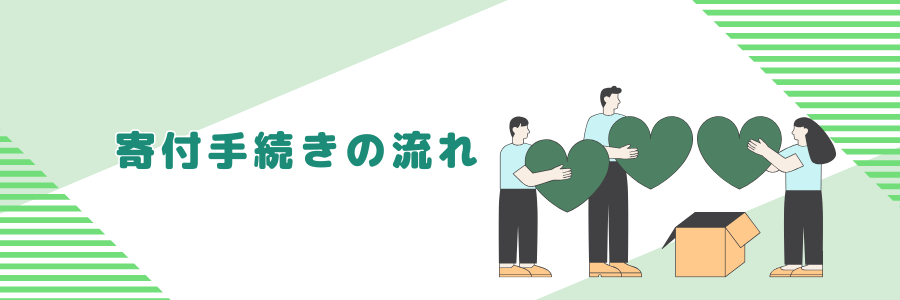
まず、寄付を検討している団体について情報収集を行います。
団体の信頼性を確認し、相続税の優遇措置や所得税の寄付金控除の対象となるかどうかを慎重に調査しましょう。
団体の具体的な活動内容は、公式ホームページやパンフレットで確認することができます。近年は、遺贈寄付に特化したパンフレットを提供している団体も増えています。
団体の活動内容をパンフレットなどで確認し、寄付先が決定したら、その団体へ連絡を取りましょう。相続税の優遇措置を受けるには、相続開始後10ヶ月以内に税務署へ申告する必要があり、その際に「領収書」が必須となります。
寄付先の団体へ「相続財産からの寄付を検討している」と伝えれば、申告に必要な領収書を優先的に発行してもらえる場合があります。さらに、相続人や故人の意向をふまえた上で、最適な支援方法を提案してくれることもあります。
団体から指定された振込先口座などの情報に従って、寄付の手続きを行います。
寄付先の団体に寄付金が届くと、「寄付金受領証明書」が発行されます。
「寄付金受領証明書」とは、財産の贈与を受けた内容や年月日、財産の明細などが記載されている書類です。国や地方自治体、公益法人、NPO法人に寄付した際に発行されます。
相続財産を取得した場合は、相続税の申告が必須となります。
前述した「寄付金受領証明書」を添えて申告期限内(相続開始後10ヶ月以内)に税務署へ申告することで、寄付した財産は非課税となります。
なお、学校法人または地方独立行政法人に寄付した際には、特定の公益法人に該当する旨を証明する書類も併せて提出しなければなりません。
寄付金控除は所得税と住民税に関する手続きであるため、相続税の非課税措置とは別途、確定申告での手続きが必要です。
確定申告は、寄付をした年の翌年2月16日から3月15日までの期間に、給与所得や事業所得などと併せて行います。会社員で年末調整を済ませている場合でも、寄付金控除を受けるためには年末調整時に発行された源泉徴収票を添付して、確定申告を行う必要があります。
相続税の免除規定を利用する場合は、相続税申告書の14表に「寄付日」「遺産の種類」「寄付先」「相続人の氏名」などを記載し、「寄付金受領証明書」を添付しましょう。銀行振込で現金を寄付した場合は、振込証明書も併せて添付することをお勧めします。
相続税申告と同様に、学校法人または地方独立行政法人への寄付の場合は、特定の公益法人としての該当性を証明する書類も添付が必要です。
【参考】国税庁ホームページ 相続税の申告書の第14表 申請書フォーマット
給与所得者等が5団体以内の自治体にふるさと納税をする場合、所得税・住民税の控除についてワンストップ特例制度を利用できます。
この制度では、所定の申請書と必要書類を寄付先の自治体に郵送するだけで税額控除を受けることができます。ワンストップ特例を利用した場合、所得税の寄付金控除は受けられませんが、寄付額から2,000円を差し引いた全額が住民税から控除され、確定申告も不要となります。
寄付金控除による還付の対象は所得税分のみとなります。住民税も控除の対象になりますが、所得税の確定申告内容に基づいて自治体が課税額を調整することで適用されます。住民税の減額は、寄付を行った翌年6月から翌々年5月までの期間に反映されます。
寄付金控除を受ける際は、ふるさと納税との関係にも注意が必要です。ふるさと納税は名称に「納税」とついていますが、税務上は「寄付」として扱われ、寄付金控除の対象となります。そのため、相続人による寄付とふるさと納税の合計額が控除額の上限を超えた場合、超過分については所得税・住民税の節税効果を受けられません。
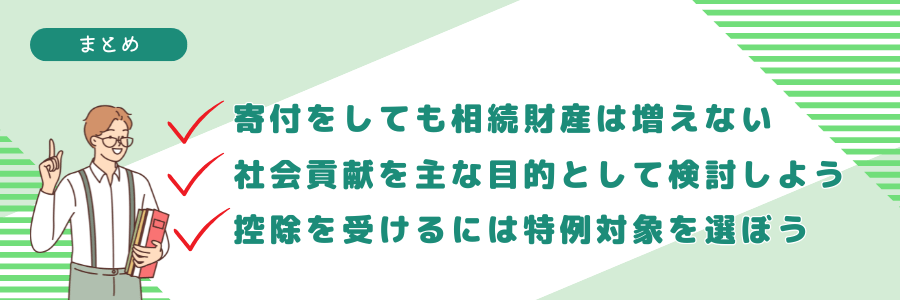
相続財産を寄付することで相続税は軽減されますが、寄付した分だけ実質的な相続財産も減少することになります。また、相続財産の寄付による非課税効果は限定的です。
そのため、相続財産を寄付する際は社会貢献を主な目的として検討するのが良いでしょう。相続財産の金額をできるだけ多く確保したいという目的での寄付はお勧めできません。
また、控除を受けるためには、特例の対象となる寄付先を選択する必要があります。寄付先によっては税負担の軽減措置が適用されない場合もあるので注意が必要です。
具体的な控除額は個人の状況によって大きく異なるため、寄付を検討される場合は、事前に専門家へ相談することをお勧めします。みなと相続コンシェルでは、税理士と司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。
【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】
東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室