相続専門コラム
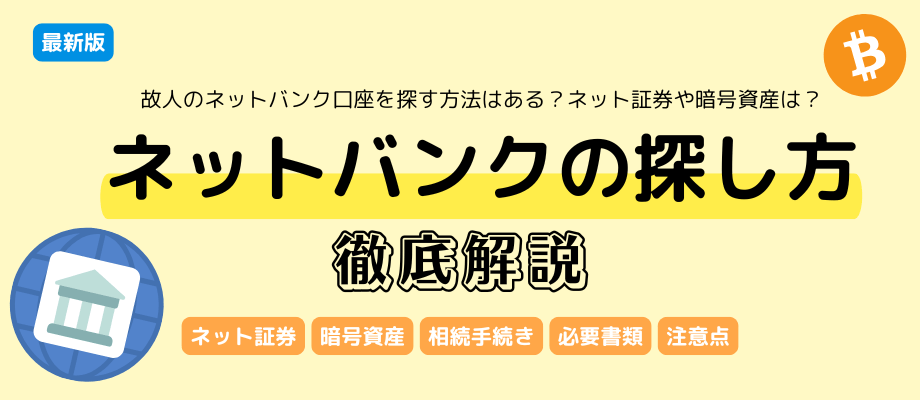
「故人がどこのネットバンクに登録しているか分からない」「通帳のない銀行口座をどうやって探せばいいんだろう?」こうした疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、故人のネットバンク・証券・暗号資産口座を探す方法、ネットバンク口座の相続手続きをする方法と必要書類、ネットバンク口座の相続対策等を分かりやすく解説します。
この記事を読み進めることで、故人のネットバンク口座の探し方と相続手続きの進め方が分かる助けとなれれば幸いです。ぜひご覧ください。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

最近ではすっかりお馴染みとなったネットでのバンキングシステムですが、実はネットバンクというのは対面のやり取りも行えるような従来の店舗窓口がない銀行の事を言います。
つまり、メガバンクなどはこのネットバンクには含まれません。比較的新しい銀行スタイルのネットバンクは窓口を置かない代わりに運営コストが圧縮されている分、以下のようなメリットとデメリットがあります。
ネットバンクは従来型の銀行と比較して、
といった利便性の高さが特徴です。また、金利が比較的高く、オンライン専業銀行ならではの特典も充実しています。
メリットが大きい一方で、相続の視点から立つと以下のようなデメリットがあります。
一般的に通帳レス=通帳を作らないため、故人がどの金融機関に口座を持っていたのか把握することが難しく、相続手続きの際に大きな課題となります。特に、故人が情報を残していない場合、口座の特定に時間がかかることがあります。
相続人がネットバンクの存在に気づかなかった場合、故人の財産を相続することができません。また、相続手続き後にネットバンク口座が見つかった場合、遺産分割協議や相続税申告等をやり直す必要が出てきます。

よって、ネットバンクは相続時に少し苦労する場合があるのです。では、どのように探せばよいのでしょう?
実は、2024年末から始まった「口座管理法」によって、マイナンバーと紐づけられた銀行口座は金融機関またはマイナポータルから一括で特定することが可能になりました。ただし、本制度は始まったばかりなので浸透するまでには時間を要することが予想されます。
上記の制度が浸透していない現時点で、残念ながら故人の口座を一括で照会する方法はありません。そのため、以下の方法を組み合わせて調査する必要があります。故人の生活や取引の痕跡を丹念に探していくことで、ネットバンクやネット証券口座の存在が見つかる可能性が高まります。
次に、具体的な調査方法について解説します。
机の引き出しやタンス、定期券入れや財布など、故人の所持品や遺品の中からキャッシュカードを探してください。キャッシュカードが見つかれば、そのカードの発行元の金融機関で口座が開設されていることが分かります。
ネットバンクの場合も多くはATMを使用するためのキャッシュカードを発行しているため、重要な手がかりとなります。
故人のスマートフォンを確認すると、ネットバンクのアプリがインストールされている可能性があります。アプリのアイコンを確認し、楽天銀行やジャパンネット銀行等のネットバンクのアプリが見つかれば、そこに口座が開設されていた可能性が高いです。
故人の自宅や書類保管場所を探し、ネットバンクからの郵便物や口座開設時の資料がないかを確認しましょう。特に、口座開設時の契約書類や取引明細書、ネット証券の場合は取引報告書や配当金通知書などが重要な手がかりとなります。
故人のパソコンを確認し、ブラウザの閲覧履歴やブックマークからネットバンクのウェブサイトにアクセスした形跡がないか調べましょう。また、パソコン内に保存された取引明細書のPDFファイルなども重要な手がかりとなります。
故人のメールアカウントにアクセスできる場合は、受信トレイを確認してください。ネットバンクからの取引通知メールや口座開設時の確認メール、定期的な残高通知などが保存されている可能性があります。特に、メールの検索機能を使って「銀行」「口座」などのキーワードで検索すると効率的です。
故人がエンディングノートを作成していた場合、そこにネットバンクの口座情報が記載されている可能性があります。エンディングノートには、金融資産の情報や口座番号、アクセス方法などが記載されていることがあるため、故人の自宅や書類保管場所を丁寧に探してみましょう。
既存の金融機関の通帳や取引明細書を確認することで、ネットバンクへの送金履歴や入金履歴を見つけられる可能性があります。特に、給与振込や定期的な引き落としの記録から、取引のある金融機関を特定できることがあります。
株式会社証券保管振替機構(ほふり)では、故人名義の上場株式等の口座開設状況について、相続人(法定相続人、法定相続人の法定代理人、法定相続人の任意代理人)からの請求に基づいて開示を行っています。
この制度を利用することで、故人が口座を開設していた証券会社等の一覧を確認することができます。開示請求には、相続人であることを証明する戸籍謄本等の書類が必要となります。
ただし、銘柄については開示されないため、各証券会社に個別に開示請求を行う必要があります。
主要なネットバンクに問い合わせる
主要なネットバンクに1件ずつ直接問い合わせをすることで、故人名義の口座の有無を確認できます。ただし、この作業には相当の時間と労力を要します。
主要なネットバンク一覧
同僚や友人知人に協力を依頼する
故人の同僚や友人知人に、取引のあった金融機関やネットバンクについて何か知っていることがないか、情報提供を依頼することも有効です。
10年以上放置され休眠口座となった場合や破綻した銀行の口座がある場合、「預金保険機構(預金者の保護や金融機関の破綻処理を担う認可法人)」が預金を保護している可能性があります。
このような場合は調査依頼が必要となりますが、預金保険機構は個人からの直接の問い合わせには対応していないため、弁護士や金融機関を通じて照会する必要があります。
故人が暗号資産(仮想通貨)を保有していた可能性がある場合は、スマートフォンやパソコンに暗号資産取引所のアプリやブックマークがないか確認しましょう。その他の調査方法についてはネットバンクと同様です。主要な取引所としてはbitFlyer、Coincheck、GMOコインなどがあります。
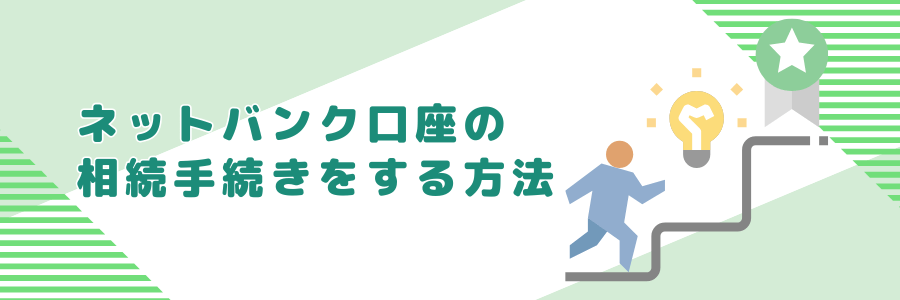
ネットバンク口座が見つかった場合は、できるだけ早く相続手続きを開始することが重要です。相続人が確定してから速やかに金融機関に連絡することで、口座の凍結や解約などの必要な措置を適切に行うことができます。
相続手続きの際は、まずネットバンクのカスタマーセンターに電話やメールで連絡を取り、必要な手続きや提出書類について確認します。専用フォームから必要情報を入力・送信すると、必要書類についての案内を受けられる場合もあります。
多くのネットバンクには相続専用の窓口があり、手続きをスムーズに進めることができます。
ただし、オンラインサービスに不慣れな高齢の相続人にとって、ネットバンクの相続手続きは難しい場合があります。そのため、インターネットやデジタル機器の操作に慣れた子ども世代の協力を得ることをお勧めします。協力を得ることが難しい場合は行政書士などの専門家に相談してみましょう。
続いて、死亡診断書や戸籍謄本等の必要書類を提出します。これらの書類は原則として原本の提出が必要です。以下の章で具体的な必要書類について解説します。

一般的に必要となる書類は以下の通りです。ただし、金融機関によって要求される書類が異なるため、必ずネットバンクに事前確認しましょう。
遺産分割協議書がある場合は、以下の書類が必要となります。
遺言書も遺産分割協議書もない場合、上記のうち遺産分割協議書以外のものを提出します。
遺言書がある場合は、以下の書類が必要となります。
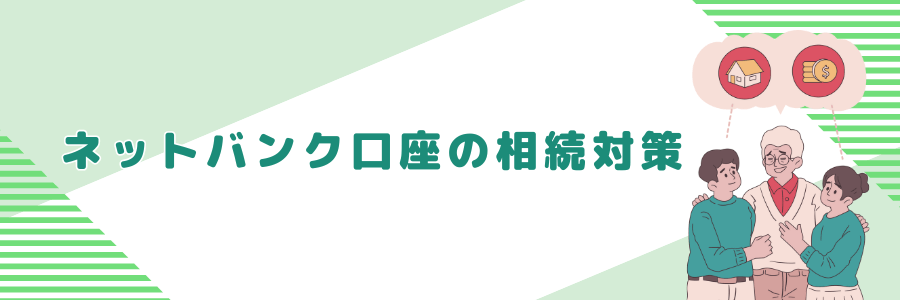
遺言書を作成することは、ネットバンク口座の相続をスムーズに進めるための重要な対策の一つです。通常、遺言書には「財産目録」を添付します。財産目録とは、遺言書に添付する文書で、被相続人が所有する全ての財産(不動産、預貯金、有価証券、貴金属など)を詳細に記載したリストのことです。
このリストに保有するネットバンク口座の情報(金融機関名、支店名、口座番号、IDなど)を記載し、相続人が確実に口座を把握できるようにしておきましょう。ネットバンクのキャッシュカードも遺言書と一緒に保管しておくと良いでしょう。
パスワードについては、セキュリティ上のリスクを避けるため、記載は控えることをお勧めします。
エンディングノートを作成し、ネットバンク口座の情報を記録しておくことも有効な対策です。エンディングノートには、利用しているネットバンクの名称、口座番号、支店名、口座の用途(給与振込用、投資用など)、定期的な入出金の有無などを詳しく記載しましょう。
また、インターネットバンキングの利用ID(ログインID)も記載しておくと、相続人が口座を特定する際の手がかりになります。パスワードについては、こちらもセキュリティ上のリスクを避けるため、記載は控えることをお勧めします。
相続人となる可能性が高い家族や親族に対して、ネットバンクや証券口座の存在を事前に伝えておくことも重要です。特に、普段から利用している主要な口座については、取引の目的や残高の概要、口座へのアクセス方法などの基本的な情報を共有しておくと良いでしょう。
ただし、セキュリティの観点から、パスワードなどの重要な情報は別途管理する必要があります。
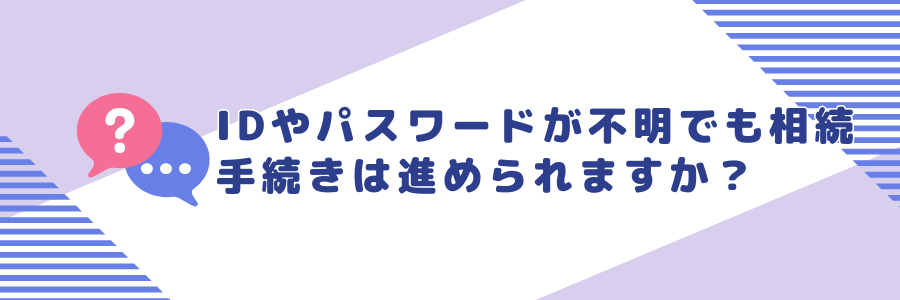
はい、IDやパスワードが不明でも相続手続きを進めることは可能です。
金融機関に対して、故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)や本人確認書類を提出することで手続きを行うことができます。ただし、金融機関によって手続き方法は異なりますので、該当するネットバンクのカスタマーサービスに相談しましょう。
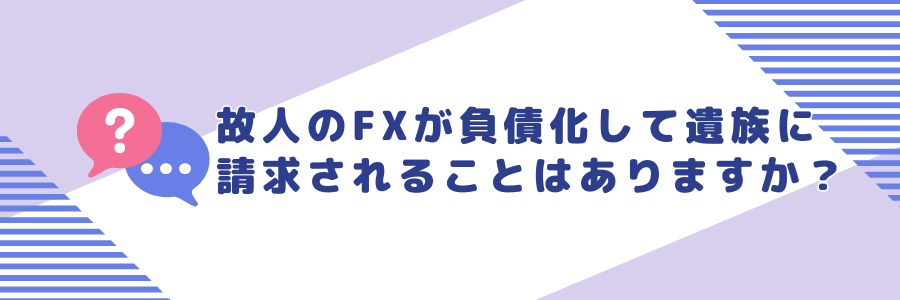
FXなどの証拠金取引は相場により負債化する可能性がありますが、遺族への請求は極めて稀です。また、負債化した場合は金融機関から連絡が入るため、過度に不安に感じる必要はありません。
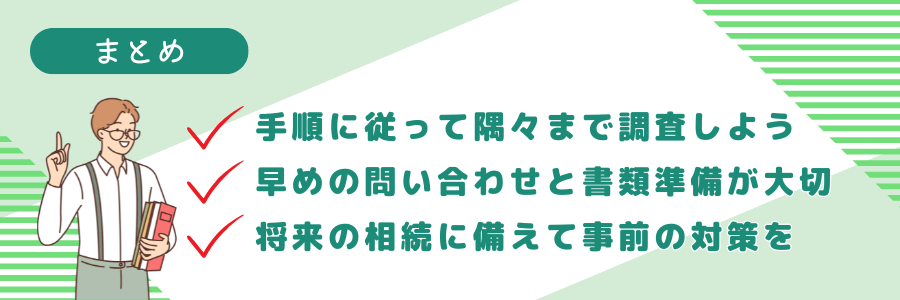
故人のネットバンク口座を探す方法として、キャッシュカードやメール履歴の確認、スマートフォンのアプリ、郵便物のチェックなど、様々な手段があることを解説してきました。「故人のネットバンク・証券口座を探す方法」の章でご紹介した手順に従って、隅々まで調査しましょう。
また、相続手続きを円滑に進めるためには、金融機関への早めの問い合わせと必要書類の準備が重要です。さらに、将来の相続に備えて、エンディングノートを作成したり家族と情報を共有したりするなど、事前の対策を講じることをお勧めします。
ご不明な点があればお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。
【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】
東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室