相続専門コラム
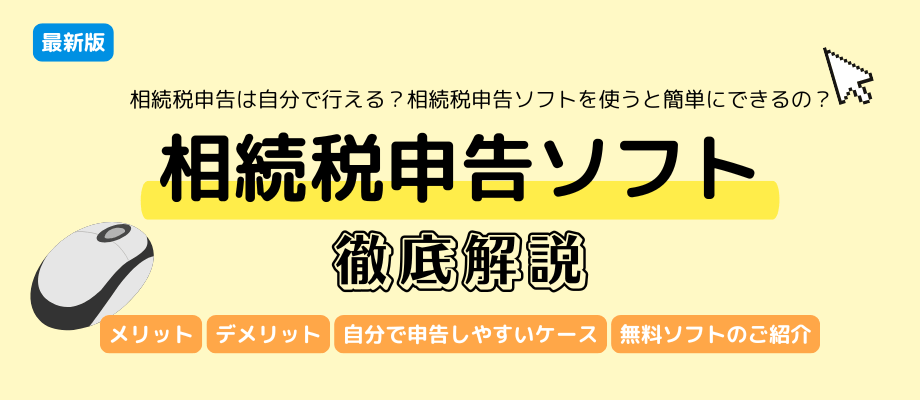
「相続税申告は自分で行えるものなのだろうか?」「相続税申告ソフトを使うと簡単に申告できるのかな?」こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続税申告ソフトの概要、相続税申告ソフトを使うメリット・デメリット、相続税申告ソフトの選び方、自分で相続税申告しやすいケースまで分かりやすく解説します。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。
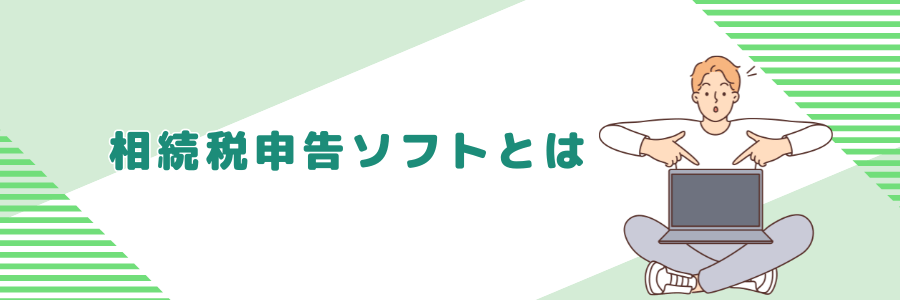
相続税申告ソフトとは、相続税の申告書作成を効率的にサポートするためのツールです。
相続税の申告書は非常に複雑で、その様式は50種類以上にも及びます。国税庁は「相続税の申告のしかた」というマニュアルを提供していますが、そのマニュアルだけを頼りに申告書を作成しようとすると、手順が複雑すぎて途中で断念してしまう可能性が高いでしょう。
なお、所得税や贈与税などは国税庁の無料システムで申告書を作成できますが、相続税については手書きするか民間企業の相続税申告ソフトを利用する必要があります。
相続税申告ソフトを使えば複雑な計算や書類作成の手間が大幅に軽減され、専門知識がなくても画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成することができます。
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」に財産情報を入力すると、相続税申告のおおよその要否と税額を確認できます。申告が必要かどうか迷っている方は、こちらのツールをご利用ください。
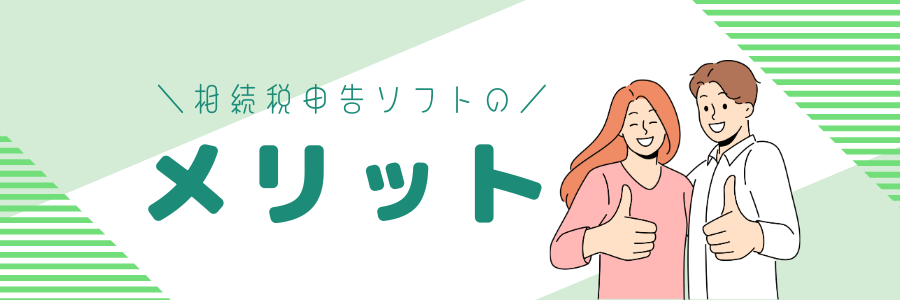
相続税申告ソフトを利用すると、専門的な税務知識がなくても、画面の案内に沿って必要な情報を入力するだけで申告書を作成することができます。入力内容に基づいて自動計算を行い、必要な項目を埋めてくれるため、手作業による計算ミスや記入ミスを防止できます。
また、税制改正により税率が変更されることもありますが、相続税申告ソフトが最新の税率に対応してくれるため、その都度最新の情報を調べる手間も省けます。
相続税申告ソフトを利用すると、入力した情報を修正する必要が生じた場合でも、簡単に修正作業を行うことができます。
手書きの場合は修正箇所があると書類全体を作り直さなければならないこともありますが、ソフトを使えば該当箇所の数値を修正するだけで、関連する計算や書類が自動的に更新されます。
相続税申告ソフトを利用すれば、相続人名などの基本情報を一度入力しておくだけで、相続財産や債務の内容を変更しながら税額計算を何度でもシミュレーションできます。
相続税は財産分割の仕方で税額が変動しますが、相続税申告ソフトを使うと様々な分割パターンの税額を事前に試算できるため、相続税の負担が最小となるような遺産分割方法や効果的な相続対策を検討することができます。
オンライン相続税申告ソフトを利用すれば、相続人全員がシステムにアクセスして情報を共有できます。これにより、書類収集や情報入力などの作業を相続人間で適切に分担でき、相続税申告における負担の偏りを防ぐことができます。

相続税申告ソフトは便利なツールですが、相続財産の洗い出しや評価という最も重要な作業はユーザー自身が行う必要があります。
申告ソフトは入力された情報に基づいて計算を行うだけなので、財産の把握や評価が不適切だと税務調査を受ける可能性や相続税の過払いにつながる可能性があります。
多くの相続税申告ソフトには相続財産の洗い出しや評価をサポートする機能が搭載されているので、これらを積極的に活用しましょう。ただし、最終的な判断はご自身で行う必要があります。
申告に関する不明点が生じた場合、相談できるのは税理士または税務署に限られます。税理士法の規定により、ソフト運営企業は申告ソフトの操作方法についての質問には回答できますが、申告内容に関する具体的なアドバイスはできません。
申告ソフトの使用中に不明点がある場合は、まずは税務署への相談をお勧めします。税務署への相談は無料で、その指導に従って申告書を作成すれば承認される申告書となるため安心です。
より詳しい相談が必要な場合は、税理士への依頼を検討しても良いでしょう。特に複雑な家族問題が存在する場合や、名義預金など税務署から指摘されやすい財産があり、自分で十分に把握できていない場合は、税理士に任せた方が良いかもしれません。
なお、一部の申告ソフトでは、オプションとして税理士への相談サービスを利用できます。
相続税申告ソフトを利用して税務調査が発生した場合、多くのソフトでは対応サポートが標準料金に含まれていません。税務調査への対応は別途料金が発生することが一般的です。
そのため、税務調査が発生した際の立ち会い費用について、事前に確認しておく必要があります。
相続税申告書の様式は年度ごとに更新され、相続が発生した年度の様式を使用しなければなりません。ソフトによっては、税務署が受理可能な最新の様式に対応していないことがあり、その場合は手書きでの清書が必要になったり、申告書が受理されなかったりする可能性があります。
そのため、ソフトを選ぶ際は、税務署提出用の正式な様式に対応しており、最新版に更新されているかを必ず確認してください。

相続税申告ソフトを利用すれば相続税の申告手続きを大幅に効率化できますが、相続税申告の難易度は財産の種類や金額で大きく変わります。本章では、自分で相続税申告しやすいケースについて解説します。具体例を挙げると、以下のような場合は自分で相続税申告をしやすいケースであると言えます。
夫の財産である5,000万円を相続したAさん。法定相続人は自分1人だけであり、基礎控除は3,000万円+(600万円×1)=3,600万円ですが、配偶者控除(1億6千万円までは相続税が非課税となる制度)を適用することで相続税額はゼロになりました。相続した財産は預貯金のみで、申告期限まで6ヶ月以上の余裕があったこともあり、Aさんは相続税申告ソフトを活用してスムーズに申告を終えることができました。
それでは続いて、このケースをもとに、どのような場合に自分で相続税申告しやすいのかについて詳しく解説していきます。自分で申告できるかどうかの判断材料として、ぜひ参考にしてください。
税額軽減特例や控除の適用で相続税額がゼロになる場合は、自分で申告しやすいケースであると言えるでしょう。特に配偶者控除は控除額が大きいため、計算に少し誤りがあって価額が増えてしまった場合でも、控除適用範囲内で相続税額がゼロのままであれば追徴課税のリスクが低く、安心して申告することができます。
相続人が1人あるいは少ない場合、遺産分割の調整や相続税の計算が比較的容易になります。当事者間での協議もスムーズに進めやすいため、自分で申告しやすいでしょう。一方で、相続人が複数いて遺産分割の話し合いが難航するなど、複雑な家族問題が存在する場合は税理士に任せた方が良いかもしれません。知識と経験のある第三者が介入することで、トラブル防止につながることもあります。
相続財産に評価の難しい財産がない場合(預貯金や株式が中心の場合)は相続財産の評価がシンプルになるため、自分で申告しやすくなります。
反対に、不動産の評価には複数の方式があり、専門知識が必要です。「路線価方式」や「倍率方式」の選択を誤ると、税額が大きく変わる可能性があります。減額要素が適用される土地がある場合は、事例に応じて計算を補ってくれる土地評価に対応したツールの活用が有効になります。
また、不動産は特例を適用することで税額を抑えられる場合があります。例えば「小規模宅地等の特例」を適用すると、一定の要件を満たした不動産の評価額は最大80%減額になります。さらに、不動産には他にも評価を減額できるポイントが多数存在しています。ただし、不動産の数が多いと計算が複雑になりますし、専門知識がない場合は判断が難しいでしょう。
財産評価の誤りによる過少申告や延滞税などの追徴課税、あるいは逆に特例を適用せずに相続税を支払い過ぎるリスクを避けたい場合、相続税申告書作成のサポートとして土地評価だけを専門家に任せることも可能です。
万が一税務調査が発生した際に立会いだけ依頼したい場合は税理士立会いサービスを検討しても良いかもしれません。
ちなみに「AI相続」であれば、計算に必要な情報を入力するだけで自動計算できる「路線価補正ツール」や万が一の時のための「税理士立会サービス」なども提供しております。
相続税申告は相続開始を知った日から10ヶ月以内に申告する必要があります。時間に余裕がある場合は自分で相続税申告を進めやすいでしょう。
反対に、申告が3ヶ月以内に迫っているなど、期限が迫っている場合も自分で相続税申告をした方が良いケースになります。期限が迫っている場合はそもそも税理士が依頼を受け付けていなかったり、割増料金がかかったりすることがあります。費用を抑えたい場合はまず自分で挑戦し、難しいと感じたら税理士への依頼を検討するという方法をおすすめします。
税理士への依頼料は財産総額によって支払う金額が変わる料金体系が採用されることが多いですが、明瞭で一律な料金をご希望される場合は「シンプル相続」のご活用もご検討ください。
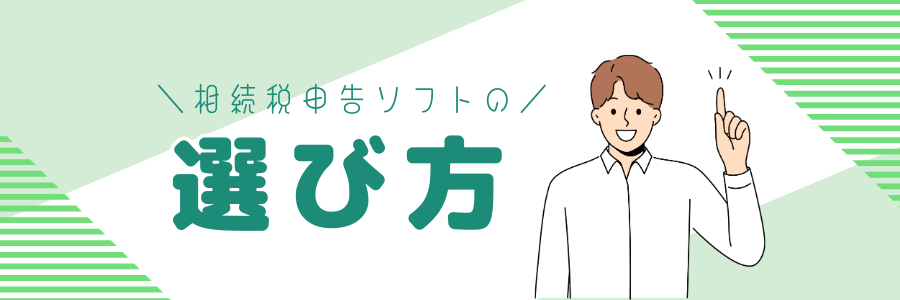
有料・無料に関わらず、申告ソフトを選ぶ際は「必要な機能が備わっているか」「入力画面が分かりやすく使いやすいか」「信頼できる申告ソフトか」「いざというときのサポートが充実しているか」という観点から判断することが重要です。
ご自身の状況やサポートの必要性を考慮して、適切なソフトを選択しましょう。
相続税申告ソフトには、個人向けと会計事務所向けに作られた専門家向けの2種類があります。
個人向けソフトは直感的な操作で初心者でも使いやすい設計ですが、搭載機能は基本的なものに限られています。一方、専門家向けソフトは複雑な計算や特殊なケースに対応できる高度な機能を備えていますが、専門知識が必要で操作が複雑です。
個人で相続税申告を検討している場合は、必ず個人向けのソフトを選択するようにしましょう。
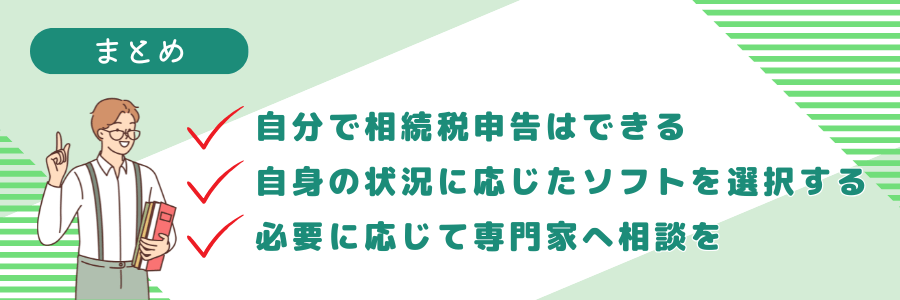
相続税申告ソフトについて、そのメリットとデメリット、選び方のポイントを詳しく解説してきました。個人で申告を行う場合は、自分の状況に合わせて適切なソフトを選択することが重要です。相続人や相続税額が少なく、複雑な相続財産がない場合は個人での申告を進めやすいでしょう。反対に、申告内容が複雑で難易度が高い場合は、必要に応じて専門家のサポートを検討することもお勧めします。
ご不明な点があればお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。
【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】
東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室