相続専門コラム
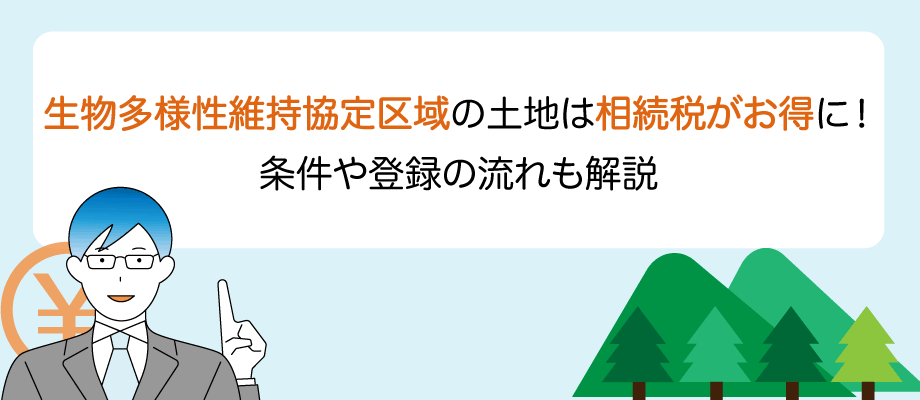
2025年の税制改正で施行された「地域生物多様性増進法」によって、生物多様性協定区域にある土地は相続税・贈与税の評価額が2割減額されることになりました。ただし、さまざまな条件があるため、どのような土地でも減額されるというわけではありません。
今回は、生物多様性維持協定の概要や区域内の土地と相続との関係、相続税対策として協定の対象となるための登録方法について解説します。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

生物多様性維持協定とは、2025年の税制改正で施行された「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(通称:地域生物多様性増進法)」に基づいて設定された協定です。
自然を守りながら豊かな生態系を維持するため、「市町村」「活動実施者(企業やNPO法人など)」「土地の所有者」の三者で協定を結び、特定の地域で自然保全活動をおこないます。活動実施者は所有者から借りた土地で自然保全活動をおこない、市町村はとりまとめ役として両者の調整役を担います。協定の締結や国への申請、長期的・安定的な活動のサポートなども市町村の役割です。

協定区域内における具体的な活動は、里山の整備や外来生物の防除、稀少生物の保護などです。通常こういった活動では多くの法律が関係するため、複雑な手続きが必要です。しかし、この協定を締結することで手続きを簡素化でき、自然保全活動をスムーズに進められるようになります。

生物多様性維持協定と相続税は一見無関係のように思われる方もいるはずです。ここからは、生物多様性維持協定によってなぜ相続税がお得になるのかを解説します。
生物多様性維持協定では、活動実施者が長期にわたって自然保全活動をおこなうことが前提となっています。相続によって所有者が変わっても土地を継続して貸してもらえるように、生物多様性維持協定区域の土地は相続税の優遇措置がとられます。

生物多様性維持協定区域内の土地を相続・贈与した場合、一般的な土地の評価額から20%減額できます。例えば、評価額が1,000万円の土地であれば200万円が控除されるため、評価額は800万円となるというわけです。この特例措置を受ける場合は、相続税の申告書に協定に関する書類などを添付する必要があります。

生物多様性維持協定区内の土地の相続税評価額を減額にするためには、以下の条件を満たす必要があります。

(1) 法第22条第1項に規定する生物多様性維持協定区域内の土地であること
参考:国税庁「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」
(2) 生物多様性維持協定に次の事項が定められていること
① 貸付けの期間が20年であること
② 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
③ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと
つまり、生物多様性維持協定で相続税評価額が減額となるのは、以下のような土地です。

自然豊かな地域に土地を所有している場合、生物多様性維持協定の区域に入って相続税減額措置を受けたいと考える人もいるかもしれません。手続きは簡単ではありませんが、以下のような流れで生物多様性維持協定の締結は可能です。

参考:独立行政法人 環境再生保全機構「認定申請(申請したい方)」
申請から認定までは6~7カ月程度かかることがほとんどです。また、生物多様性維持協定が締結されると、正当な理由がない限り土地は貸付けを継続することになるため、自身で使ったり売却したりすることができなくなります。

2025年の税制改正によって、生物多様性維持協定を締結した土地は相続税・贈与税が2割減額されることになりました。相続税がお得になるので、自然豊かな地域に土地を所有している方は興味を持つかもしれません。しかし、貸付けの期間は20年、正当な理由がなければ原則的に貸付けを更新することなど、条件は厳しいものになっています。
使い道のない土地を所有している、所有している土地にかかる相続税が気になるという場合、必要に応じて税理士などの専門家に相談しましょう。経験豊かな専門家であれば、もっと現実的な解決策を提案してくれるはずです。手続きに時間がかかることもあるため、不安なことがある場合は時間に余裕を持って早めに相談することをおすすめします。
相続診断士・終活カウンセラー・AFP(日本FP協会認定)の資格を保有し、相続・終活分野に特化した記事を多数執筆。実家の相続および遺品整理の経験をもとに、当事者の視点と専門知識の両面を活かした情報提供を行っている。制度や税制、手続きをテーマに、読者にとって「正確でわかりやすい」記事作成を心がけている。
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室