相続専門コラム

「相続税申告は他の相続人と共同で行った方がいいのかな?」「あるいは、一人ずつ単独で申告した方が良いのだろうか?」こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続税申告書は共同申告がオススメである理由、共同申告する場合の相続税申告書の書き方、単独で提出することはできるのか、共同申告が適切でないケース、単独申告する場合の注意点・対処方法・相続税申告書作成のポイント、よくある質問まで分かりやすく解説します。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

相続人が複数存在する場合、相続税申告書は全員が1つの申告書に連名で提出することをオススメします。法律で義務付けられているわけではありませんが、8割以上の相続人が連名方式を選択しています。
令和3年度の税制改正により、相続税申告書をはじめとする税務関係書類の押印義務が廃止されました。これにより、連名での申告書提出手続きが大幅に簡素化されました。
改正前は相続人全員の押印が必須とされ、押印がない申告書は無効とみなされていました。改正後は、マイナンバーの記載と提出意思の表明により申告意思を判断することになりました。ただし、旧式の申告書を使用して押印した場合でも、申告の効力には影響ありません。

本章では、共同申告(連名提出)をする場合の相続税申告書の作成方法について詳しく解説します。
連名で申告する相続人の「氏名・住所・マイナンバー」を、相続税申告書の「第1表と第1表(続)(以降、第1表等)」に記載します。共同申告する相続人のみ記載し、共同申告しない相続人については記載しないのがポイントです。共同申告しない相続人は別途、申告書を単独で提出しなければなりません。
なお、第1表の相続財産には、共同して申告書を提出しない相続人も含む、全ての相続人等に係る合計額を記入する必要があります。

※引用:国税庁 | 複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法
全ての相続人の氏名や金額等を第1表等に記載する場合、共同申告しない相続人の氏名欄横にある「参考(参考として記載している場合)」に〇をつけます。この場合、共同申告しない相続人のマイナンバーは記載不要です。〇で囲まれた相続人分は申告書として扱われません。
第1表等に全ての相続人の氏名や金額を記載する場合、共同して申告書を提出しない相続人等の氏名及び金額欄を斜線で抹消することも可能です。この場合もマイナンバーの記載は不要です。

相続税申告書は一般的に連名で提出(共同相続)されますが、中には共同申告が困難になってしまうケースも存在します。以下でご紹介するケースのように、相続人間の不仲や争いがある場合は、別々に申告(単独申告)することも可能です。
資料収集の初期段階では協力的な相続人たちも、遺産分割協議の過程で対立することがあります。特に、現預金が少なく遺産の大部分が不動産である場合、その分割方法をめぐって意見が分かれ、共同申告の実施が困難になるケースがあります。
相続税申告には相続人全員の関与が必要となります。しかし、疎遠な相続人と連絡が取れない場合や、書類の準備に非協力的な相続人がいることもあります。何度連絡を試みても応答がなく、申告期限の関係上やむを得ずその相続人を除いて申告書を提出せざるを得ないケースが極稀に存在します。
稀なケースですが、他の相続人が依頼した税理士の信頼性に対して疑問がある場合、共同申告が困難になることがあります。また、相続人同士の関係が悪化している場合、相互不信に陥って単独申告を選択するケースもあります。
こちらも稀なケースですが、親と同居していた長男が預貯金などの遺産を隠すことがあります。長男が相続税申告時に「これが全ての遺産です」と言って一部の預貯金しか開示せず、その金額が明らかに少額な場合、兄弟姉妹は共同申告を拒否することがあります。例えば、同居していた長男が父からの金銭を兄弟から隠していて、後の税務調査で追徴課税となるようなケースです。
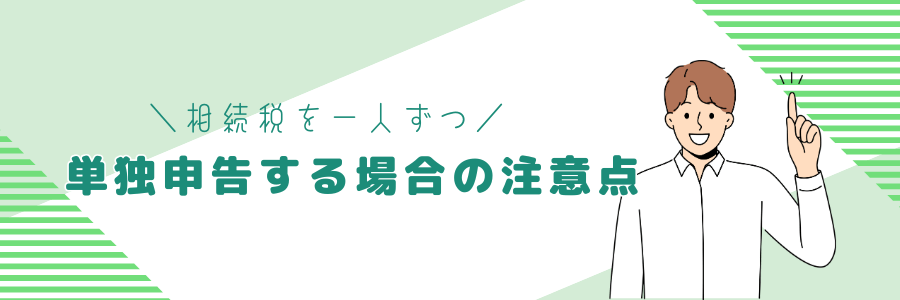
単独申告は共同申告より多くのリスクを伴うため、本章では単独で申告する場合の注意点について解説します。
同居していた相続人と別居していた相続人では、被相続人に関する情報量に大きな差が生じます。相続税を単独で申告する場合、この情報格差によってさまざまな問題が発生する可能性があります。具体的な例を以下でご説明します。
「相続開始前7年以内の贈与」と「相続時精算課税贈与」は相続税の課税対象です。これらの金額は申告書に含める必要があり、贈与を受けていない相続人の相続税額も増加します。
7年以内の贈与は相続税申告の対象になります・生前贈与加算について
同居していた相続人は被相続人の金融口座や取引先について直接知る機会があり、詳しい情報を把握できる一方、別居していた相続人はこれらの情報を得にくい状況にあります。
さらに、固定資産税の課税明細書は所有者の自宅宛てに送付されるため、別居していた相続人は財産内容を正確に把握することが難しくなります。
遺言書は紙で保管されているため、被相続人の保管場所が不明な場合は発見が困難です。特に、親から子への事前の告知がない場合、同居していない相続人は遺言書の存在を把握できないことがあります。
また、同居していた相続人が自身に不利な内容の自筆証書遺言を破棄してしまうケースもあり、他の相続人は気付かないまま遺産分割協議を進めてしまうことがあります。ただし、公正証書遺言であればこの問題は防ぐことができます。
相続税の計算において、「障がい者控除」や「未成年者控除」の適用により納付税額がゼロとなるケースがあります。この場合、控除枠に余りが生じることがあり、その余剰分を他の相続人(扶養義務者)へ移すことが可能です。
ただし、この配分は相続人間の協議により決定する必要があります。協議が整わない場合は、算出税額の按分により自動的に計算されることになります。
なお、障がい者手帳を所持していない相続人でも、一定の要件を満たせば控除を適用できる場合があります。しかし、相続争いが生じている状況では、このような情報を相続人全員で共有し、最適な活用方法を協議することは困難です。
【相続税の未成年者控除】 要件や控除額の計算方法、複数回利用する場合の注意点等
相続人が個別に申告書を提出した場合、同一の相続に対して異なる内容の申告書が税務署に提出されることとなります。土地の評価額は特に解釈が難しく、税理士によって大きな差が出ることもあります。相続財産の評価額についての解釈が異なる場合は納税額に差が生じ、税務調査の対象となるリスクが高くなります。
税務調査の結果、過大納付であれば返還請求が可能ですが、申告漏れや納税額の誤りがあった場合は過少申告加算税が課されます。さらに、相続税申告期限後に納税する場合は、過少申告加算税だけでなく延滞税も課されることになります。不要な手間と費用が発生する恐れがあるため、注意が必要です。

相続人が個別に税理士へ相続税申告を依頼すると、それぞれに報酬が発生します。税理士報酬は遺産総額に応じて決まりますが、例えば共同申告なら80万円で済むケースでも、2人が個別に申告すると160万円となってしまいます。このような余分な手間やコストを避けるためにも、共同申告をお勧めします。
申告期限(相続開始から10か月以内)までに遺産分割協議が終わらない場合は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を適用することができません。これにより、当初納付する相続税額が一時的に高額となります。
財産の分割が終わっていない場合も期限内に相続税申告を行う必要があるため、特例の適用できるようにするためには「3年以内の分割見込書」を添付する必要があります。なお、還付を受けるためには遺産分割確定後4カ月以内に更正請求を行う必要があります。
また、遺産分割が確定するまでは不動産売却ができない点も課題となります。そのため、できるだけ早期に遺産分割協議を進め、合意形成を図ることが重要です。
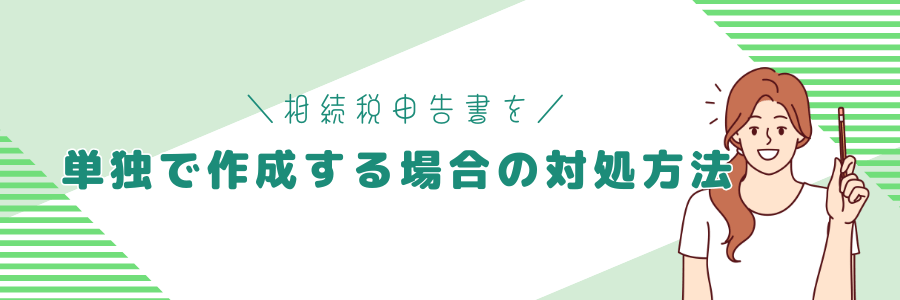
単独で相続税申告書を作成せざるを得ない場合は、以下のような対処方法があります。まずはできる限り他の相続人との情報共有を図り、財産の全容把握に努めることが重要です。それでも協力が得られない場合は、専門家のサポートを受けながら可能な限り正確な申告を目指します。
他の相続人への贈与を調べたい場合、「被相続人が利用していた金融機関の取引履歴を取り寄せて資金移動がないか確認する」「相続税法49条に基づく開示請求を行う」「弁護士に調査を依頼する」などの方法が有効です。
遺産分割協議は相続人全員が集まって行うことが望ましいですが、連絡が取れないケースもあります。そのような場合は、登記簿謄本(全部事項証明書)や不動産や金融商品の残高証明などから財産の種類や評価額を確定し、「未分割申告」として法定相続分で申告を行います。
財産の分割が未確定の場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」は適用できません。これらの特例を利用するためには、「3年以内の分割見込書」を添付し、遺産分割確定後4カ月以内に更正請求を行う必要があります。
相続人の中には、自分だけが受取人となっている生命保険金、生前贈与(3年分)、死亡退職金など、他の相続人に知られたくない情報を持っている場合があります。
これらの情報は遺産分割協議書等には記載されませんが、こうした情報を隠して個別申告をした場合、申告内容の相違が発生して税務調査の対象となり、修正申告と加算税の支払いが必要になる可能性があります。
税務調査では最終的に全ての財産が明らかになるため、相続人全員で情報を開示し、内容を確認し合うことが望ましいでしょう。

単独で相続税申告書を作成するためのポイントは、「相続人同士が協力し合う」ことです。
相続人同士の協力と連絡が円滑な申告の鍵となります。被相続人も望んでいたはずの良好な関係を維持することが大切です。たとえ争族(相続を巡って相続人同士が対立し、紛争状態になること)に発展しても、相互理解を通じて和解を目指すことが望ましいでしょう。
理想としては共同申告が望ましいですが、やむを得ず個別申告をする場合でも相続人同士で情報を綿密に共有し、申告内容に齟齬が生じないように注意しましょう。これにより、不要な費用や修正作業を防ぐことができます。

通常、相続税申告書は相続人全員による共同申告が基本となります。相続人同士の関係が良好な場合は、一つの申告書による共同提出をお勧めします。
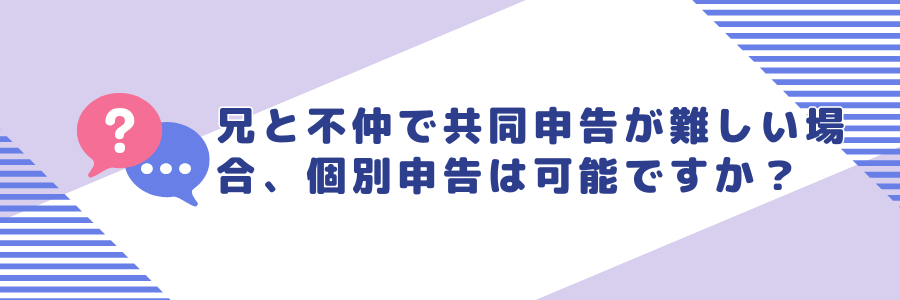
別々の税理士に依頼すれば個別申告することは可能ですが、申告内容に相違があった場合は税務調査のリスクが高まります。
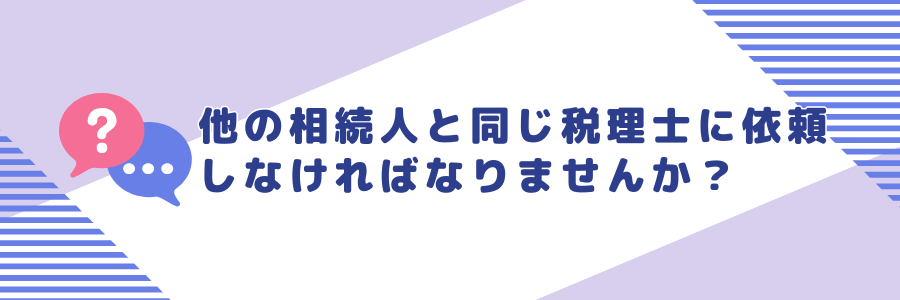
通常は相続人全員で1つの申告書を作成し、1人の税理士に依頼することが一般的です。ただし、税理士の信頼性に疑問がある場合や申告内容について相続人間で意見が異なる場合は、別々の税理士に依頼して個別申告をすることも可能です。

はい、別々の税理士に依頼することになるため、相続人ごとに税理士報酬が必要となります。
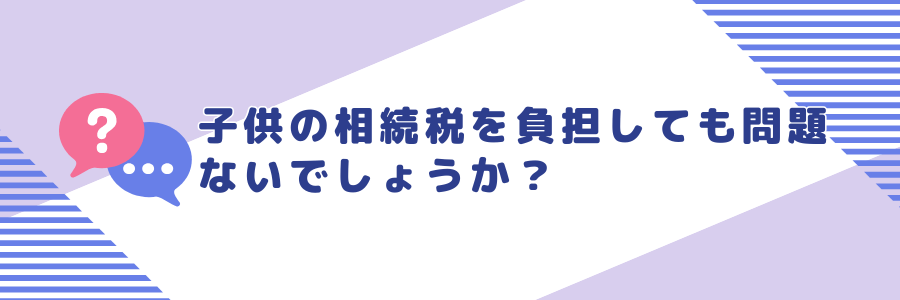
子供の相続税を負担する場合、その負担分は贈与とみなされます。110万円を超える場合は贈与税が発生し、二次相続時には贈与か相続財産かの判断が必要となるため、慎重な対応が求められます。
また、生命保険金受取人(愛人や故人の配偶者の兄弟姉妹など)の相続税を共同申告のために負担する場合も、同様に贈与とみなされます。

相続放棄をした場合でも相続税の計算上は法定相続人としてカウントされるため、配偶者控除や基礎控除には影響しません。ただし、次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)が新たな相続人となった場合は相続税額の加算(20%加算)など、相続放棄により税負担の増加が生じる可能性があります。
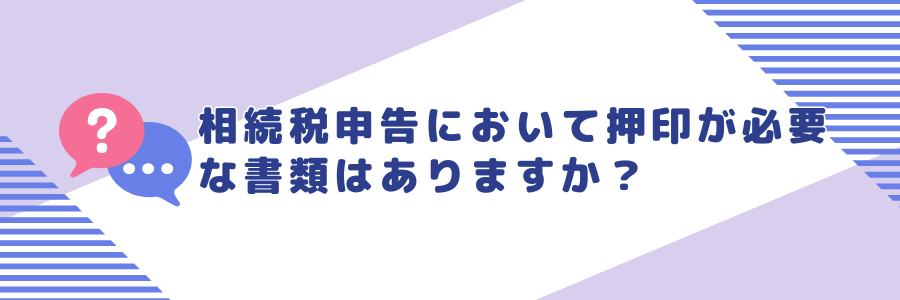
相続税申告書への相続人の押印は不要ですが、一部の添付書類には引き続き押印が必要です。
延納申請等の「担保提供関係書類」および「物納手続関係書類」には押印が必要となります。具体的には「納税保証書」「抵当権設定登記承諾書」「所有権移転登記承諾書」等が該当します。これらの書類には、実印の押印および印鑑証明書の添付が必要です。
相続税や贈与税の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)を受けるには、「財産の分割の協議に関する書類(遺産分割協議書等)」への全相続人の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
【ひな型】相続税申告における遺産分割協議書の書き方を徹底解説
代理人が納税証明書の交付請求等をする際の委任状は押印不要ですが、特定個人情報の開示請求および閲覧申請手続に係る委任状には押印が引き続き必要です。
振替依頼書およびダイレクト納付利用届出書には、引き続き金融機関の届出印(銀行印)が必要となります。ただし、e-Taxで提出する場合は押印は不要です。
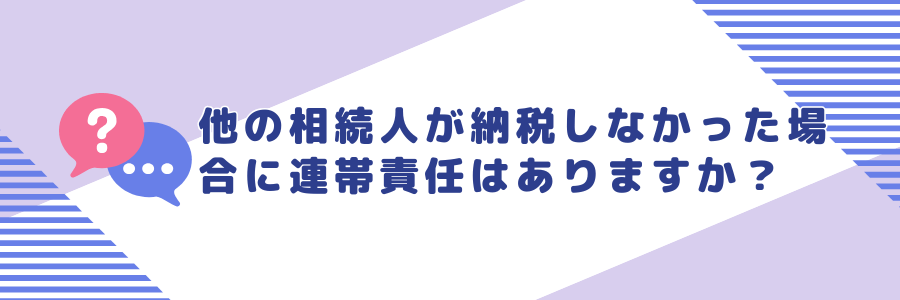
相続人が複数いる場合、相続人同士は互いに連帯納付義務があります。相続税の未納が発生した場合、税務署から他の相続人に通知が送られます。自身の相続税を既に納付済みであっても、自身が相続した財産額を上限として、他の相続人の未納分を納付する必要があります。
この連帯納付義務は相続税の申告期限から5年間続きます。この期間中に税務署から連帯納付の通知や督促を受けた場合は、全額の納税義務が発生します。ただし、申告期限から5年が経過するまでに通知がない場合、この義務は免除されます。
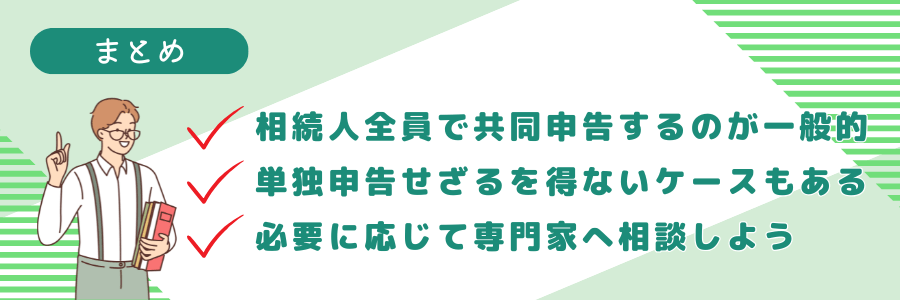
相続税申告は、相続人全員で共同申告するのが基本ですが、状況によっては単独申告が適する場合もあります。共同申告は税務調査のリスクを抑え、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用しやすくしたり、相続税申告に関する余計な手間やコストを削減できるメリットがあります。
一方、相続人同士が対立している場合には、単独申告を選択せざるを得ないこともあります。単独申告では申告内容の整合性が取りにくく、税務調査対象となって追加徴税を課されるリスクがあるため、慎重に進める必要があります。
最適な相続税申告の方法は個人の状況によって異なるため、迷った場合は専門家のアドバイスを活用しながら進めることをおすすめします。ご不明な点があればお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。
【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】
東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室