相続専門コラム
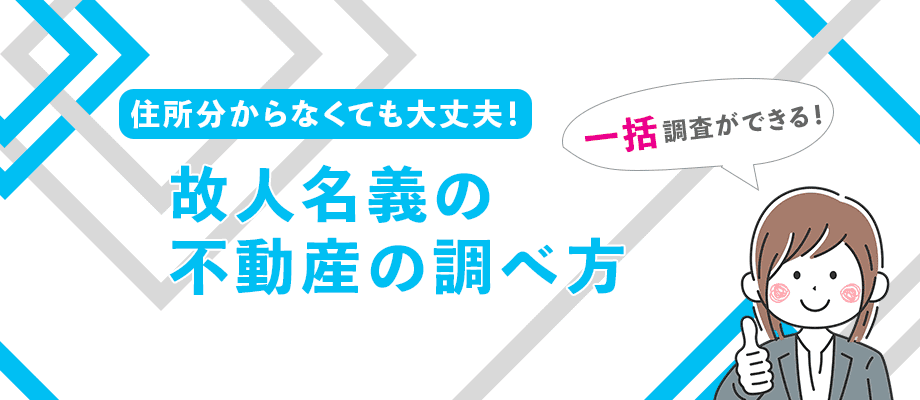
亡くなった人が所有していた不動産は、相続財産として遺産分割協議の対象になります。
相続不動産を放置していると思わぬペナルティを受けることもあるため、不動産情報は漏れなく把握しなければなりません。そこで今回は、故人名義の不動産情報を調べる方法を解説します。実は市区町村単位で一括調査できるスグレモノも。
「亡くなった親が地方に不動産を所有していたはずだが、詳細がわからない」、「故人は複数の不動産を所有していたので、どこから調べればいいかわからない」といった疑問・お悩みに対応できるよう努めております。ぜひご覧ください。
目次
無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!
複雑な計算もAI相続におまかせ。
さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。
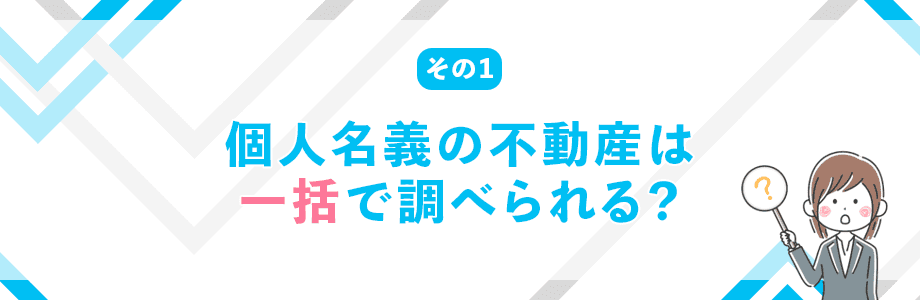
相続される方は恐らく「故人(被相続人)が所有していたのは土地か建物なのか、所在地はどこなのかまったく見当も付かない」といった状態であると推察します。
特に多くの不動産を抱えていた場合、固定資産税納税通知書では一覧表が分かりやすく届くわけでもない上、そもそも非課税の不動産に関しては通知すら来ないのです。
でもご安心下さい。そんな状態でも調べる方法があります。
それは、市区町村の窓口で「土地・家屋名寄帳」を取得することです。
名寄帳(なよせちょう)とは、市区町村が作成する台帳のことです。課税対象になっている土地や家屋などの固定資産情報(1月1日時点の情報)が所有者ごとにまとめられています。相続人(または代理人)であれば、所定の必要書類を提出することで被相続人の名寄帳を取得・閲覧できます。
ちなみに名寄帳は市区町村ごとで管理されているため、一括で受け取れる情報は対応して貰った窓口の市区町村の不動産に限られます。それでも預貯金の調査と比較するとかなり調べやすいと言えるでしょう。
※名寄帳の取得には1通200円~300円程度の手数料がかかります
※市区町村によっては名寄帳の発行・閲覧はせず固定資産税・都市計画税の課税明細書を再発行することで対応している場合もあります
なぜ不動産を調査する時に「名寄帳」が最適となるのか。そのワケをより詳しく解説していきましょう。主に以下の5つが挙げられます。
不動産情報がわかる登記事項証明書の取得には、土地の正確な地番が必要です。しかし、名寄帳は氏名さえわかっていれば、被相続人に紐付く同一市区町村内の不動産を一覧で確認できます。
前述した通り、毎年送付される固定資産税納税通知書には非課税不動産の記載はありません。名寄帳であれば自治体によって非課税不動産が記載されていることもあるため、所有不動産を見落とす可能性を抑えられます。
したがって、手がかりが少ないときは真っ先に「名寄帳」を調べる事が故人名義の不動産を調べるためのスマートな方法と言えるでしょう。
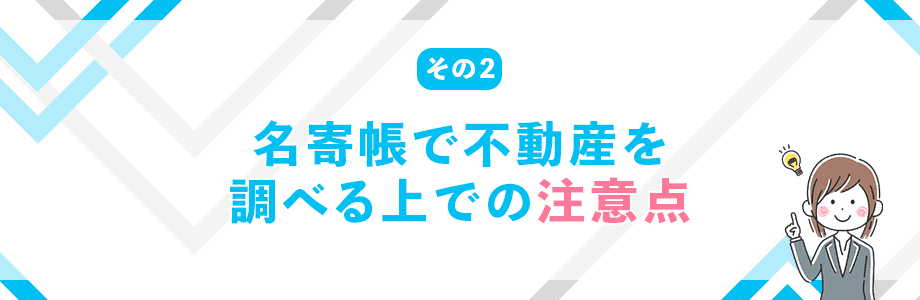
ここまでメリットばかりを記載してきましたが、もちろんそれだけではないのが実情です。名寄帳を取得する際に注意しておきたいポイントが幾つか存在します。以下の5つです。
主に被相続人名義ではない場合と、非課税の不動産についてです。
また、市区町村単位での一括取得は可能ですが、他の市区町村にも不動産があると少し大変です。名寄帳の注意点について順番に確かめておきましょう。
最初に記載した通り、名寄帳は自治体ごとに管理されているため同一市区町村内における不動産情報しかわかりません。
被相続人が他の市区町村に不動産を所有していた場合は、他の市区町村でも名寄帳を取得する必要があります。他の市区町村にある不動産については、固定資産税の納税通知書や権利証などで情報を確認してください。
名寄帳には共有名義の不動産情報も記載されますが、市区町村によっては共有名義と単独名義の台帳が別々になっていることもあります。また、共有名義の不動産情報の記載があっても、共有持分の割合については記載がないこともあるので要注意です。
不動産が共有名義の場合、共有持分も調べなければ正しい相続税評価ができません。名寄帳取得の際は窓口で「共有名義の不動産情報も取得したいこと」を伝えましょう。共有持分割合の記載がなければ、法務局で登記事項証明書を取得して正しい持分割合を確認してください。
「名寄帳を取得したものの、所有家屋の中に自宅の記載がない」場合は、自宅の名義が先代名義になっている可能性があります。
先代名義かどうかは、先代名義の名寄帳を取得するか、自宅の登記事項証明書を取得することで確認できます。名寄帳に「あるはずの不動産情報がない」ときは、先代名義の可能性があるのでご注意ください。
名寄帳に記載されている不動産は個人名義のみとなるため、法人名義の不動産は記載されません。
被相続人が経営者であったり、不動産管理法人を持っていたりする場合は、法人名義の不動産についても調査が必要です。このような場合は、法人名義の名寄帳を別途取得してください。
前述通り、市区町村によっては、私道や農地など一部の非課税不動産が名寄帳に載っていないことがあります。特に気を付けたいのは、被相続人の自宅が私道に隣接しているケースです。
自宅が私道に隣接している場合は、自宅とあわせて私道の名義変更(相続登記)手続きをする必要があります。名寄帳に記載がなければ登記事項証明書で私道の権利関係を確認し、必要な手続きをすませてください。
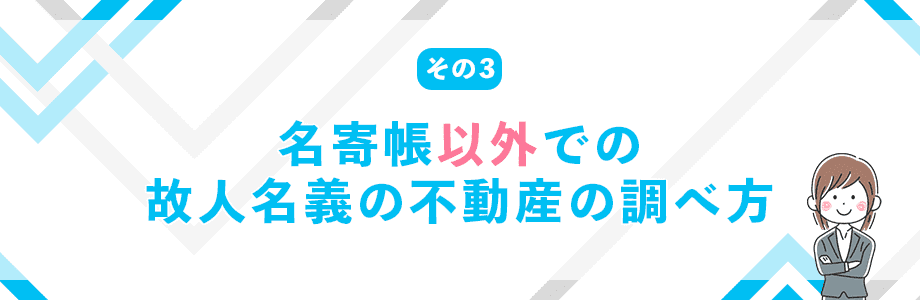
故人の不動産を調べる方法の最適解として「名寄帳」から触れて話を進めてきましたが、念の為にその他の不動産の調べ方についても確認しておきます。名寄帳は各市区町村の市役所でしか取得できませんので、手近な場所から調査したい場合は以下の方法もご検討下さい。
もし被相続人が不動産の謄本を手元に揃えていたなら、最も有力な手がかりとなります。というより所有権等の権利を確認する上で登記事項証明書は一番正確な書類と言えるかもしれません。
というのも、非課税の私道に関しては名寄帳でも確認が出来ない可能性があるのですが登記事項証明書であれば誰が所有しているかを確認できるからです。名寄帳に非課税の不動産が記載されているかどうかに関しては地方自治体によって異なりますのでご注意下さい。
ただし、日付が古いと所有権そのものが変更されている可能性がありますので、もし古い登記事項証明書を見つけた場合は最新のものを「法務局」で取得しましょう。
毎年必ず発行され、支払いが必要となる固定資産税の納税通知書。固定資産税は1月1日の不動産の所有者に対して課税されます。最新年度の通知書の名義が被相続人のものなら間違いありません(贈与していても生前贈与加算で相続税対象となります)。
通知書は相続発生日後すぐに届くわけではないので、被相続人が遺していた書類からまずは探すことになります。また、固定資産税の課税対象となる不動産が対象ですので仮に山林や原野などで非課税の不動産は確認できません。
固定資産税の納付としては口座引落が一般化しつつあります。よって、通知書を探さなくても固定資産税の対象となっている不動産に関しては銀行口座の履歴を遡ることで確認することが出来ます。
もちろん、固定資産税納税通知書よりも更に情報が少なく、支払われた事実しか確認はできません。よって履歴によって固定資産税の支払いを確認した場合は名寄帳などを取り寄せて、より詳細を確認していくことになるでしょう。
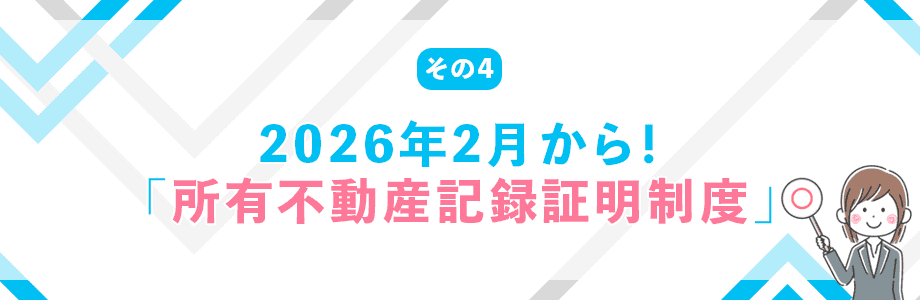
2024年現在、相続不動産の調査は名寄帳が有効ですが、2026年2月以降は「所有不動産記録証明制度」を活用できるようになります。
所有不動産記録証明制度は、被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧でリスト化する制度です。市区町村を問わず全国の不動産情報を確認できるため、自治体ごとに名寄帳を確認する必要がなくなります。
2024年4月1日以降、過去の未登記不動産も含めてすべての不動産の相続登記手続きが義務化されました。2024年4月以前に相続した不動産の登記手続きの最終期限は、2027年3月31日です。申請期限の前に改めて所有不動産記録証明制度を活用すれば、登記手続きが必要な不動産を改めて確認できます。
所有不動産記録証明制度は2026年(令和8年)2月2日に施行予定のため、詳細は自治体や法務省のサイトでご確認ください。
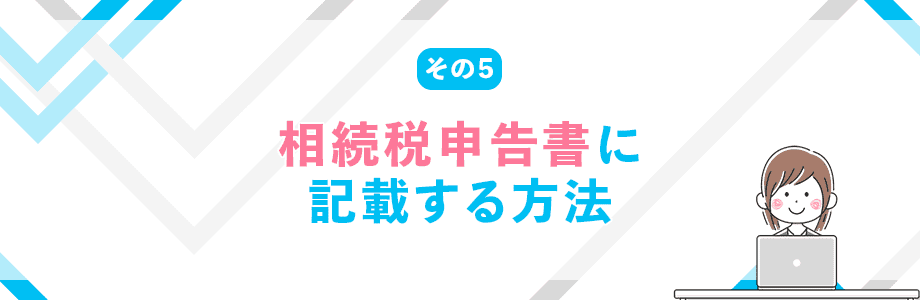
調査で把握した不動産の相続税評価額を求めたら、他の相続財産と合算します。合算した金額が相続税の基礎控除額以上であれば、相続税申告が必要になります。
不動産情報は、相続税申告書第11表の付表1「相続税がかかる財産の明細書(土地・家屋等用)」に書きます。小規模宅地等についての特例を受ける場合は、「第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」も必要です。
監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室